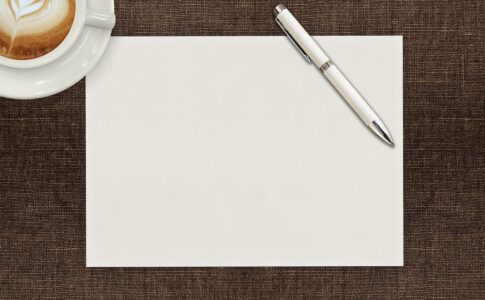<この記事は約 13 分で読めます>
税務調査は、税務署が企業や個人の税務申告に対して行う確認作業です。
税務調査は毎年9~11月及び4~5月に行われることが多い傾向にあります。
この記事では、以下について解説します。
- 税務調査とは
- 税務調査の流れ
- 税務調査の対策
税務調査は適切に対応しなければ、問題点を指摘されて、多額の追徴課税を請求される可能性があります。税務調査が入っても冷静に対応できるよう、日々の記帳や申告書は税理士にチェックしてもらうと良いでしょう。
東京・大阪で税務調査の対策でお困りの方は、一度ハートランド税理士法人へご相談ください。無料で相談に乗らせていただきます。
税務調査とは

税務調査とは、国税局や税務署が納税者の申告内容を確認し、正確な税金の申告や納付が行われているかを調査する制度です。税務調査には、主に定期的な「任意調査」と、脱税や不正行為の疑いがある場合に行われる「強制調査」があります。
任意調査
任意調査は税務署や国税局が行う通常の税務調査で、主に納税者が適切な申告や納税を行っているかを確認するために実施されます。任意調査は、一部を除いてほとんどが事前に調査の日程が通知されるため、納税者は準備する時間があります。調査の対象となるのは申告書や帳簿、請求書、領収書などの書類で、調査官が申告内容の妥当性を検証します。
任意調査は特定の問題や疑惑がある場合だけでなく、ランダムに選ばれた企業にも行われることがあります。
強制調査
強制調査とは悪質な脱税が疑われる場合に行われる、税務当局による厳格な調査手続きです。国税局の査察官が裁判所の発行する「捜索差押許可状」に基づき、納税者の同意を得ずに強制的に実施します。強制調査では、帳簿や契約書などの書類だけでなく、パソコンやスマートフォンに保存されているデータも対象となり、証拠の押収が行われることがあります。
通常の任意調査とは異なり事前の通知はなく、突然訪問されることが特徴です。強制調査の対象となるのは架空取引や利益の意図的な隠蔽など、重大な脱税が疑われるケースに限られます。なお、調査の結果、重大な違反が確認されると追徴課税や罰金、さらには調査件数の6割~8割は検察庁への告発に発展します。
税務調査はいつ行われる?
 税務調査が実施される時期に明確な決まりはありません。多くの事業者は、決算後や確定申告後に税務調査が来ると考えることが多いですが、実際には年間を通じて調査は行われます。
税務調査が実施される時期に明確な決まりはありません。多くの事業者は、決算後や確定申告後に税務調査が来ると考えることが多いですが、実際には年間を通じて調査は行われます。
なお、税務署の繁忙期である2月から3月の確定申告期間は調査を避け、9~11月及び4~5月に調査が集中する傾向が見られるものの、これはあくまで目安です。また、税務署が疑わしい取引や不自然な経費計上などを発見した場合、時期に関係なく調査が実施されることもあります。さらに、業界の状況や事業規模、過去の申告内容によっても調査時期は左右されます。
税務調査の多い時期

税務調査は9〜11月に調査が行われることが多いとされています。
法人と個人事業主の場合で違いはあるのか、なぜ9〜11月に行われることが多いのかということを詳しく解説していきます。
法人の場合
決算期が2~5月の法人は9~11月が多く、決算期が8~翌年1月の法人は調査は4~5月が多い傾向にあります。
ただ、決算期を3月にしている法人がほとんどのため、税務署側の業務が落ち着き始める9〜11月に集中することが多いでしょう。
また、調査が入る頻度に決まりはありませんが、一般的に3〜10年に一度調査が行われると言われています。
個人事業主の場合
個人事業主の場合も3月に確定申告を行うケースが多いので、調査は7〜11月に集中する傾向にあります。その期間の中で特に入る確率が高い時期は7〜8月です。
調査が入る頻度の目安は、5〜10年に一度と言われています。
個人事業主の税務調査についての詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
【関連】税務調査は個人事業主にもくる!調査に入られやすい個人の特徴とは?
各月毎の税務調査に入られる可能性
9〜11月以外の時期も税務調査に入られる可能性はあるものの、実際に入られることは稀でしょう。ここからは、その理由についてみていきましょう。
1月〜3月
法人の年末調整や個人事業主の確定申告を行う時期です。税務署の職員は多忙な時期になり、調査を行う余裕はほとんどないため、この時期に税務調査が入る確率は低いと言えるでしょう。
4〜6月
法人は3月を決算期にしているケースがほとんどです。この時期の税務署職員も法人税の申告処理などの業務に追われていることが多いですが、8~1月決算の法人の税務調査の時期でもあります。
7〜8月
7月は税務署の人事異動があり調査職員のチーム編成が行われるため、調査に入るというよりも調査に入る法人を選定する時期と言えます。一方で、個人事業主の調査は法人に比べると短期間で終わるため、個人事業主を中心に調査を行うこともあります。
9〜11月
この時期は税務調査が本格的に始動するため、税務調査が最も入りやすい時期となります。
12月
年末年始を控えているため、税務署及び法人や個人事業主側も多忙になる時期です。調査が入る確率は低いでしょう。
税務調査の対象
 税務調査の対象は法人・個人事業主を問わず、税務署が必要と判断した事業者全般です。特に、過去の申告内容に不備や不正の疑いがある場合は調査対象になるリスクが高まります。また、売上や利益の変動が大きい事業者、経費が異常に多く計上されているケース、業界平均と比較して異常な申告が見られる場合なども調査されやすい傾向があります。
税務調査の対象は法人・個人事業主を問わず、税務署が必要と判断した事業者全般です。特に、過去の申告内容に不備や不正の疑いがある場合は調査対象になるリスクが高まります。また、売上や利益の変動が大きい事業者、経費が異常に多く計上されているケース、業界平均と比較して異常な申告が見られる場合なども調査されやすい傾向があります。
さらに、業界内での脱税事例が報道された際や、匿名の通報や第三者からの情報提供があった場合も、税務署が調査に乗り出す可能性が高まります。そのため、業種や規模に関係なく、日々の帳簿管理と適正な申告が求められます。
税務調査の流れ
 次に、税務調査の流れを紹介します。
次に、税務調査の流れを紹介します。
- 税務署からの告知
- 調査日の日程調整
- 必要書類の準備
- 税務調査
- 税務署の指摘に対する回答
税務署からの告知
税務調査は、まず税務署からの事前告知によって始まります。この告知は電話や書面で行われ、調査の日程や場所、担当者の氏名が通知されます。通常は1週間から10日前に告知されることが多く、突然訪問されるケースは少ないです。
ただし、悪質な脱税の疑いがある場合や緊急を要する場合には、事前告知なしに抜き打ちで調査が行われることもあります。告知の際には、税務署の担当者から調査の目的や範囲、調査対象となる資料について簡単に説明されます。この段階で、不安や疑問があれば、税務署に直接質問するか、顧問税理士に相談することが重要です。告知を受けた後は、調査に備えて帳簿や資料の整理を進め、税務署の指示に従い準備を整えましょう。
調査日の日程調整
税務調査の告知を受けた後、次に行われるのが調査日の日程調整です。通常は税務署の担当者が提示する複数の日程の中から、事業者が希望する日時を選ぶ形で調整が進みます。調査日を決める際には、帳簿や書類の整理時間を確保できる日程を選ぶことが望ましいです。
また、顧問税理士がいる場合は、税理士が立ち会える日を優先して調整すると調査がスムーズに進みやすくなります。税務署からは、調査の際に準備しておくべき書類や資料のリストが事前に提示されることが多いため、リストに沿ってしっかりと用意しておくことが重要です。
必要書類の準備
税務調査の日程が決定した後は、必要書類を準備します。税務署からは事前に、調査当日に必要となる書類リストが提供されることが多いです。一般的に用意すべき書類には、総勘定元帳、仕訳帳、決算書、納税申告書、請求書、領収書、契約書、預金通帳の写しなどです。
これらの書類は、税務署の担当者が事業活動の実態や会計処理の正確さを確認するために使用します。特に帳簿の記載内容と証憑書類が一致していることが重要です。書類の不備があると追加の調査や説明が求められる可能性が高まります。顧問税理士がいる場合は、書類の準備や確認をサポートしてもらうと良いでしょう。
税務調査
税務調査当日は税務署の調査官が事業所やオフィスに訪問して調査が開始されます。調査の最初には、事業概要や経営者の役割についてヒアリングが行われることが一般的です。その後、帳簿書類や証票の確認が進められます。
また、現金残高の確認や在庫の実地調査が行われる場合もあります。税務署の調査官は、経理担当者や顧問税理士に対して質問をしながら調査を進めます。調査が無事に完了すると、その後の対応や修正申告の必要性についての説明が行われ、税務調査が終了します。
税務署の指摘に対する回答
税務調査の過程で税務署の調査官から帳簿や証票の内容に不備や疑問点が見つかった場合、経営者や経理担当者はその指摘に対して回答する必要があります。税務署からの質問は、取引の背景や金額の根拠、経費の内容に関するものが多く見受けられます。正確な説明ができるよう事前に顧問税理士と連携して調査に備えておくことが重要です。
税務調査は時期によって内容に違いはあるのか

税務調査の時期による内容の変化は基本的にありません。
税務調査が入る前には事前通知が来るので、税務調査の開始日時、調査場所、調査対象の税目、期間などを決めます。
税務調査当日は、挨拶後に事業概要などの説明を求められ、その後調査が開始されます。調査官から質問されたり、帳簿書類などの提出を求められたりするでしょう。
税務調査後は、調査の2〜3週間後に来る結果を待ちます。
詳しい税務調査の内容については下記の記事をご覧ください。
【関連】税務調査とは?任意調査と強制調査の違い、調査の流れや調査に入られやすい会社について
税務調査の対策
 次に、税務調査の対策のために以下2つの内容を解説します。
次に、税務調査の対策のために以下2つの内容を解説します。
- 税務調査に必要な書類
- 税理士への相談
税務調査に必要な書類
税務調査に必要な主な書類は以下の通りです。
- 法人税申告書(個人事業主は所得税の申告書)
- 登記簿謄本
- 決算書
- 総勘定元帳
- 売掛、買掛帳
- 現金出納帳
- 固定資産台帳
- 預金通帳
- 棚卸明細表
- 契約書、請求書、領収書
- 源泉徴収簿
- 給与台帳など
税理士への相談
税務調査が実施される前や調査日は顧問税理士と相談し、帳簿や申告内容に問題がないか確認しておくことが大切です。税理士は税務調査の専門知識を持ち、税務署の調査官がどのような点を重点的に調べるかを理解しています。
適切な準備をすることで調査がスムーズに進む可能性が高まるでしょう。また、税理士は必要な書類や証拠を整える手助けをしてくれるため調査中に生じる疑問点や問題に迅速に対応できます。税務調査が始まる前から税理士とのコミュニケーションを密にしておくことで、調査中の不安やリスクを最小限に抑えることができます。
大阪で税務調査の対策なら国税庁OBも働くハートランド税理士法人へ

今回は、税務調査が行われることが多い時期や流れについて解説しました。
税務調査の時期は、個人事業主、法人ともに毎年9〜11月及び4~5月に行われることがほとんどです。調査内容に関しても大きな違いはありません。
税務調査に備えるためには税理士に相談し、申告内容や帳簿に問題がないか事前に確認することが重要です。税務調査がスムーズに進むようサポートを受けられるでしょう。
税務調査は適切に対応しなければ、問題点を指摘されて、多額の追徴課税を請求される可能性があります。税務調査が入っても冷静に対応できるよう、日々の記帳や申告書は税理士にチェックしてもらうと良いでしょう。
東京・大阪で税務調査の対策でお困りの方は、一度ハートランド税理士法人へご相談ください。無料で相談に乗らせていただきます。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。