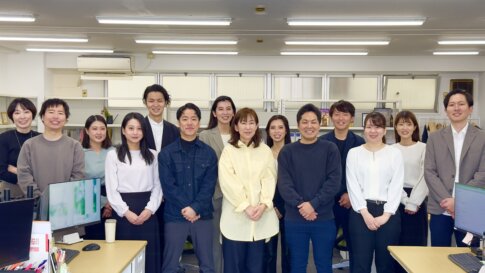<この記事は約 12 分で読めます>
税務調査は基本的に事前通知で告知され、日程を決めた後に行われます。適切な対策をしておくためにも、税務調査の流れは必ず頭に入れておきましょう。
この記事では、以下について解説します。
- 税務調査とは
- 税務調査の流れ
- 税務調査でよく確認される5つのポイント
- 税務調査を受ける際の4つの注意点
税務調査は適切に対応しなければ、問題点を指摘されて、多額の追徴課税を請求される可能性があります。税務調査が入っても冷静に対応できるよう、日々の記帳や申告書は税理士にチェックしてもらうと良いでしょう。
東京・大阪で税務調査の対策でお困りの方は、一度ハートランド税理士法人へご相談ください。無料で相談に乗らせていただきます。
税務調査とは
 税務調査は、税務署が法人や個人事業主の税務申告が正確かどうかを確認するために行う手続きです。調査には「任意調査」と「強制調査」があり、一般的には任意調査が行われます。任意調査では、税務署が対象者に事前通知を行い、日程を調整したうえで進められるのが特徴です。調査の結果、誤りが見つかれば修正申告や追徴課税が求められます。一方、強制調査は、脱税の疑いがある場合に行われ、裁判所の令状に基づき実施されます。
税務調査は、税務署が法人や個人事業主の税務申告が正確かどうかを確認するために行う手続きです。調査には「任意調査」と「強制調査」があり、一般的には任意調査が行われます。任意調査では、税務署が対象者に事前通知を行い、日程を調整したうえで進められるのが特徴です。調査の結果、誤りが見つかれば修正申告や追徴課税が求められます。一方、強制調査は、脱税の疑いがある場合に行われ、裁判所の令状に基づき実施されます。
税務調査の流れ
 はじめに、税務調査の流れを紹介します。
はじめに、税務調査の流れを紹介します。
- 税務署の調査担当者から税務調査の事前通知が来る
- 税務調査の日程を決める
- 顧問税理士と相談して対策する
- 税務調査を受ける
- 税務調査後の質問に回答する
順を追って解説するので、参考にしてください。
税務署の調査担当者から税務調査の事前通知が来る
税務調査は、基本的に税務署からの事前通知で開始されます。通知では、調査の対象期間や目的、調査担当者の情報が示されます。通知が来たら、すぐに内容を確認しましょう。特に、調査の範囲がどこまで及ぶのかを把握し、それに基づいて必要な書類を準備することが重要です。
また、調査の実施日時は税務署と相談して決定することができるため、自社の都合も考慮して対応日を設定します。顧問税理士がいる場合は通知をすぐに共有し、準備を進めるように依頼しましょう
税務調査の日程を決める
通知が来たら、税務調査の日程を決めます。調査には複数日が必要な場合もあり、通常は1~2週間程度の猶予が与えられます。この期間を活用して必要書類の整理や関係者への連絡を済ませておくことが大切です。
また、過去の申告内容や経理記録を再確認し、不備があれば事前に対策をします。日程が決まったら調査当日のスケジュールを詳細に把握し、関係者間で共有しておくことが重要です。
顧問税理士と相談して対策する
税務調査の準備には専門家の助言が欠かせません。特に、税務に詳しい顧問税理士と連携することで、調査における不備や誤解を未然に防ぐことが可能です。また、税理士は、税務署とのやり取りを代行することができるため、調査対象者の負担を大きく軽減してくれるでしょう。
調査日までに税理士と相談して、過去の申告内容で売上や仕入、経費の計上に誤りがないかを事前にチェックして調査に備えることが重要です。
税務調査を受ける
税務調査当日、税務署の調査官が指定された日時に事業所を訪問します。調査官は、経理資料や申告書を基に税務申告が正確に行われているかを確認します。この際、調査官からの質問に対しては正確かつ簡潔に答えることが重要です。不明点があれば、即答せず「後日回答します」と伝えるなど、冷静な対応を心掛けましょう。
なお、調査対象となる主な書類には、売上帳(明細表)、仕入帳(明細表)、経費帳(明細表)などが含まれます。
税務調査後の質問に回答する
税務調査終了後、税務署から追加の質問や書類提出の依頼がある場合があります。税務署からの指示に基づいて迅速に対応することが求められます。
また、調査結果に基づき修正申告や追加納税を指摘された場合は顧問税理士と相談し、適切に手続きを進めましょう。
税務調査でよく確認される5つのポイント
 次に、税務調査でよく確認されるポイントを5つ紹介します。
次に、税務調査でよく確認されるポイントを5つ紹介します。
- 前期との増減が大きな項目
- 売上の期ズレや除外
- 在庫の計上漏れ
- 計上されている経費の内容
- グループ間取引
それぞれ解説するので、税務調査前のチェックポイントとして参考にしてください。
前期との増減が大きな項目
税務調査では前期と比較して大幅な増減が見られる項目が調査対象となることも少なくありません。特に売上や経費において異常な変動がある場合、その理由や背景が詳しく尋ねられる可能性があります。前期から大きな増減が発生した場合は、適切に記録された根拠資料を用意しておくことが重要です。
たとえば、売上が急増した場合には、それが特定のキャンペーンや新規取引によるものであることを示す資料を準備することで、調査官に対する説明がスムーズになるでしょう。逆に、経費が異常に減少している場合も同様です。
売上の期ズレや除外
売上の期ズレや一部の売上が申告から除外されている場合も、税務調査で重点的に確認される項目です。期ズレとは、実際の取引が発生した時期と異なる年度に売上を計上することであり、意図的であれば不正行為と見なされます。また、売上の除外とは、特定の取引を申告に含めないことを指します。売上の除外金額が大きくなると脱税行為と見なされることがあります。
こうした行為は、事業の収益を過少申告する目的で行われるケースが多く、厳しい調査対象となります。各取引の発生日や金額を正確に記録し、帳簿と取引先の発行する書類が一致していることを確認しましょう。
在庫の計上漏れ
在庫の計上漏れも税務調査で指摘されやすい項目の一つです。在庫の管理は、売上や原価計上に直結するため、その正確性が重要視されます。特に在庫の棚卸を実施していない場合や、棚卸表が正確でない場合には、申告内容が不正確であると判断されるリスクがあります。
また、在庫品の廃棄や減耗があった場合には処理が適切に行われているかも確認されます。在庫に関する資料を整理し、廃棄証明書や在庫管理システムのデータなど、調査官に対して根拠を提示できる状態にしておくことが求められます。
計上されている経費の内容
経費として計上されている項目が、事業運営に必要な支出であるかどうかも調査の対象となります。特に高額な経費や、プライベートで使用された可能性のある経費については、詳細な説明が求められることが一般的です。
たとえば、交際費や接待費が不自然に多い場合には、その使用目的や対象者について明確にする必要があります。また、交通費や通信費などの一見すると事業経費に見える項目でも、個人的な支出が含まれている場合には否認される可能性があります。これらの経費については、領収書や契約書などの証拠書類を整理し、調査官からの質問に対して適切に説明できる準備を行いましょう。
グループ間取引
同族会社や関連企業間で行われる取引も税務調査では重点的に確認されます。グループ間取引では取引価格が適正かどうかが特に問題視されることが多く、市場価格と大きく乖離している場合には、不適切な所得移転が疑われる可能性があります。例えば、関連会社に過剰な支払いを行うことで利益を移転し、本来支払うべき法人税を回避する行為が問題となることがあります。
また、利益操作のために売上や費用の金額を意図的に操作するケースも問題がないか検証が必要です。
税務調査を受ける際の4つの注意点
 最後に、税務調査を受ける際の注意点を5つ紹介します。
最後に、税務調査を受ける際の注意点を5つ紹介します。
- 適切な応接対応をする
- 聞かれていないことを話さないようにする
- 矛盾が生じないよう回答する
- 無責任な言い訳はしないようにする
税務調査が長引いたり税務調査官から疑念を抱かれたりしないよう、目を通しておきましょう。
適切な応接対応をする
税務調査を円滑に進めるためには、調査官に対して適切な応対を行うことが重要です。訪問時には、まず名刺交換を行い、調査官の所属や氏名を確認したうえで必要な書類や質問への対応を始めます。調査官には礼儀正しく接し、業務に支障を来さないよう、調査に必要なスペースや資料を準備しましょう。
また、調査中は業務への影響を最小限に抑えるため、事業所内での動線や調査官が滞在する場所についても配慮が必要です。適切な応接対応を心掛けることで調査官に良好な印象を与え、調査がスムーズに進む可能性が高まります。
聞かれていないことを話さないようにする
税務調査では、調査官からの質問に対して正確に答えることが求められますが、聞かれていないことを余分に話すことは避けましょう。調査官の質問に対して不必要な情報を付け加えることで、調査の範囲が広がる可能性があります。
そのため、質問には簡潔に、必要最小限の情報をもって回答することが適切です。また、不明瞭な点がある場合には無理に答えを出そうとせず、「確認後に回答します」といった形で一旦保留することも一つの方法です。
矛盾が生じないよう回答する
税務調査では調査官の質問に対する回答が一貫性を持っていることが重要です。回答内容に矛盾があると調査官が疑念を抱き、さらなる追及を受ける可能性が高まります。たとえば、経費に関する説明で税理士と担当者で異なる内容を話してしまうと、その項目が重点的に調査されることになります。
事前に顧問税理士と相談し、調査対象となる可能性のある項目についての説明を準備しておくことが有効です。また、関係者間で情報を共有し、全員が同じ理解を持って調査に臨めるようにしておきましょう。
無責任な言い訳はしないようにする
調査中に問題点を指摘された場合、無責任な言い訳をすることは避けましょう。不明点やミスが見つかった場合には、正直に認め、今後の改善策を伝える姿勢が求められます。
たとえば、「担当者が知らなかった」や「忙しくて確認できなかった」といった言い訳は、調査官に悪印象を与えるだけでなく、調査が長引く要因となります。責任を明確にしつつ、誠実な対応を心掛けることで調査官との信頼関係を築き、調査を円滑に進めることが可能になります。
税務調査の対策なら国税庁OBも働くハートランド税理士法人へ
 税務調査は事業運営において避けては通れない場面ですが、適切な準備と対応を行うことで調査後のトラブルを最小限に抑えることが可能です。税務調査の際には、調査官への応接対応を丁寧に行い、聞かれていないことを話さない、一貫性のある説明を心掛けるなど、冷静で誠実な対応が求められます。
税務調査は事業運営において避けては通れない場面ですが、適切な準備と対応を行うことで調査後のトラブルを最小限に抑えることが可能です。税務調査の際には、調査官への応接対応を丁寧に行い、聞かれていないことを話さない、一貫性のある説明を心掛けるなど、冷静で誠実な対応が求められます。
税務調査を適切に乗り越えることは事業の信頼性向上にもつながります。日頃から帳簿や書類を正確に管理し、税務の専門家と連携しておくことで税務調査への備えを万全にしておきましょう。
税務調査は適切に対応しなければ、問題点を指摘されて、多額の追徴課税を請求される可能性があります。税務調査が入っても冷静に対応できるよう、日々の記帳や申告書は税理士にチェックしてもらうと良いでしょう。
東京・大阪で税務調査の対策でお困りの方は、一度ハートランド税理士法人へご相談ください。無料で相談に乗らせていただきます。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。