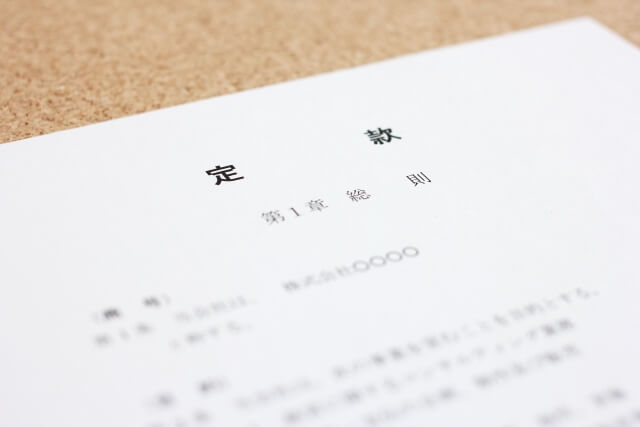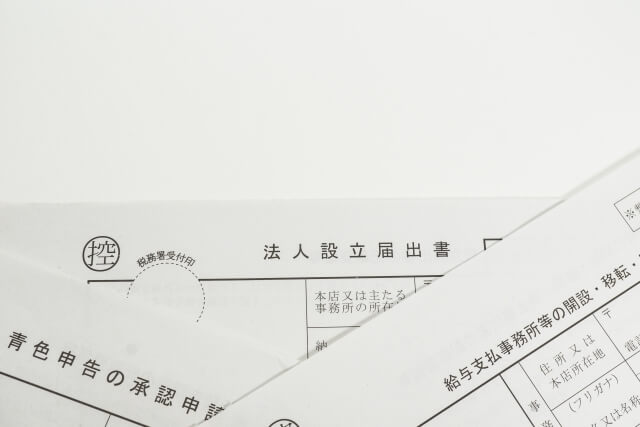<この記事は約 13 分で読めます>
「節税のためにマイクロ法人を作りたいけど、本当に効果があるの?」「社会保険料を抑える方法として勧められたけど、リスクはないの?」
そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?
マイクロ法人は、うまく活用すれば社会保険料や所得税の負担を軽減できる一方で、設立や運営にはコストや手続きの煩雑さも伴います。制度を正しく理解しないまま形式的に設立すると、税務署から「節税目的の形式的法人」と判断されるリスクもあるため、慎重な検討が必要です。
本記事では、以下の内容についてわかりやすく解説します。
- マイクロ法人とは
- マイクロ法人を作るメリット・デメリット
- 設立の具体的な手順と費用
- 脱税と判断されないための注意点
マイクロ法人の設立を検討している方、または現在の働き方や税負担に課題を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
マイクロ法人とは

マイクロ法人は特定の目的に最適化された小規模法人であり、一般的な法人や個人事業主と比較して、コストや運用面において独自の特徴を持ちます。
まずは、制度的な違いや実務上の相違点について解説します。
一般的な法人との違い
マイクロ法人は、いわゆる中小企業や株式会社といった「一般的な法人」と同じく法人格を持つものの、規模や運営目的において明確な違いがあります。
マイクロ法人の多くは従業員を雇わず、経営者1人のみで運営されるケースが主流です。
一方、一般的な法人は、複数の役員や従業員を抱え、事業拡大を前提とした組織構成が多く見られます。
また、マイクロ法人は節税や社会保険料の最適化を目的として設立されることが多く、業務実態の規模が極めて小さい点も特徴です。
個人事業主との違い
マイクロ法人と個人事業主の違いは、主に法律上の人格と税制、保険制度にあります。個人事業主は法人格を持たず、事業の責任はすべて事業主本人に帰属します。
一方、マイクロ法人は法人格を持ち、会社と個人が法律的に区分されるため、事業リスクの分離や損失の限定が可能です。
また、税制面では、個人事業主は所得税を累進課税で負担するのに対し、マイクロ法人では法人税+役員報酬による所得分散ができるため、一定条件下では節税効果が得られます。さらに、社会保険の適用も異なり、法人では厚生年金と健康保険への加入が原則必要となります。
マイクロ法人を作るメリット

マイクロ法人を設立することには、個人事業主や会社員では得られない特有の利点があります。税や社会保険料の負担軽減、経費計上の柔軟性、社会的信用の向上などが代表的です。
以下では、マイクロ法人を活用することで得られる主なメリットを3つに分けて解説します。
- 社会保険料や所得税が個人事業主より抑えられる
- 経費として使える幅が広がる
- 社会的な信用度が高まる
社会保険料や所得税が個人事業主より抑えられる
マイクロ法人では、役員報酬を低く設定することで、健康保険料や厚生年金保険料の負担を最小限に抑えることが可能です。
また、役員報酬として給与を支払うことで、法人所得と個人所得を分散でき、結果として累進課税の影響を軽減できます。たとえば、個人事業主として年間600万円を得る場合、すべてが個人所得として課税されますが、マイクロ法人なら法人所得を調整しながら節税することができます。
ただし、社会保険への加入は原則義務であり、意図的な逃れ方はリスクが伴うため注意が必要です。
また、個人事業主だと、扶養人数により保険料の上限が変わる国民健康保険に加入することになりますが、マイクロ法人だと扶養人数が増えても保険料が変わらない社会保険に加入できるのも大きなメリットになり得ます。
経費として使える幅が広がる
法人として認められることで、経費として計上できる項目の幅が広がる点もメリットの一つです。
個人事業では業務との明確な関連性が求められる一方で、法人では「役員報酬の支払い」「事務所費用」「交通費」「交際費」など、法人活動に伴う支出であれば一定の範囲で認められやすくなります。
たとえば、自宅の一部を事務所として利用している場合、家賃や光熱費の一部を経費計上することも可能です。ただし、あくまで業務実態との整合性が求められるため、領収書や契約書類の保存が必須です。
これについても、個人事業主とは違って役員報酬という形で給与を受け取ることになるため、役員報酬の金額次第とはなりますが給与所得控除を受けられることも所得税的にはメリットとなります。
社会的な信用度が高まる
マイクロ法人は法人格を有するため、取引先や金融機関からの信用力が高まるというメリットがあります。たとえば法人名義での銀行口座開設、事務所契約、融資申請などで有利に働くことが多いです。
また、法人名義の契約ができることにより、ビジネスの継続性や対外的な信頼感が増すため、BtoBビジネスや行政手続きでも対応がスムーズになります。
個人での活動では信頼を得にくい場面でも、法人としての格付けが一定の信頼性を担保してくれることが期待できます。
マイクロ法人を作るデメリット

マイクロ法人には多くのメリットがある一方で、設立や運用に伴う負担やリスクも存在します。特にコストや手続き、税務面での注意点は設立前に必ず把握しておく必要があります。
ここでは、マイクロ法人の主なデメリットを3つに分けて解説します。
- 法人設立に費用がかかる
- 赤字でも特定の税金が発生する
- 税務申告の手続きが煩雑になる
法人設立に費用がかかる
マイクロ法人を設立するには、登録免許税や定款認証費用など初期費用が発生します。株式会社の場合、定款認証費用が約5万円、登録免許税が最低でも15万円(資本金に応じて変動)必要です。
加えて、印鑑作成や開業届出に伴う諸費用が発生するため、トータルで20〜25万円程度は見込んでおく必要があります。
個人事業主であれば開業は無料で済むため、この差は小さくありません。特に節税メリットが少ない所得水準では、設立費用が逆に負担になる可能性もあります。
赤字でも特定の税金が発生する
たとえ事業が赤字であっても、法人である以上は毎年「法人住民税の均等割」を支払う義務があります。たとえば東京都23区の場合、均等割は年額7万円(資本金1,000万円以下・従業員50人以下の場合)と定められています。
これは売上ゼロでも発生する税金であり、休眠状態であっても課税対象になります。個人事業主にはこうした「赤字でも必ず支払う固定税」はないため、マイクロ法人にすることで思わぬ負担になることがあります。
税務申告の手続きが煩雑になる
マイクロ法人でも、一般法人と同じく決算書の作成や法人税申告、地方税申告など複数の手続きが必要です。これらは専門的な知識を要するため、自力で対応するのは難しく、多くのケースでは税理士への依頼が必要になります。
年間顧問料や申告報酬として10万円〜30万円程度のコストがかかるのが一般的です。手間だけでなく、経済的にも負担が増えるため、メリットとのバランスを考慮して導入する必要があります。
マイクロ法人の作り方

マイクロ法人を設立するには、通常の株式会社や合同会社の設立手続きとほぼ同様のステップを踏む必要があります。
以下では、法人設立の基本的な流れを3つのステップに分けて解説します。
- 会社の基本事項を決定する
- 定款を作成して法務局への登記申請をする
- 役所に書類を提出する
会社の基本事項を決定する
まずは、設立する会社の基本情報を決めます。具体的には、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金、会計年度、役員構成などを確定させます。これらは定款の内容にも反映されるため、慎重に検討する必要があります。
とくに事業目的は、登記の際に認められる内容でなければならないため、曖昧な表現は避けるのが原則です。また、資本金は1円からでも設立可能ですが、金融機関との取引や信用面を考慮し、10万円〜50万円程度を目安に設定するケースが多いとされています。
定款を作成して法務局への登記申請をする
会社の基本事項が決まったら、次は会社の憲法ともいえる「定款」の作成と認証手続きを行います。株式会社の場合は公証役場での定款認証が必要となり、認証費用約5万円が発生します。定款には事業目的や発起人情報、株式の取扱いなどを記載します。
定款認証後は、法務局へ登記申請を行い、会社の設立登記を完了させます。この時点で法人格が正式に付与され、会社としての活動が可能になります。
役所に書類を提出する
登記が完了したら、税務署や都道府県税事務所、市区町村などへの届出が必要になります。具体的には、「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などの書類を作成し、提出します。
また、従業員がいないマイクロ法人であっても、健康保険と厚生年金の加入手続きを年金事務所にて行う必要があります。これらの手続きを怠ると、法的なトラブルや税制上の不利益を受ける可能性があるため、設立後も速やかな対応が求められます。
マイクロ法人の設立にかかる費用

マイクロ法人を設立する際には、個人事業主の開業とは異なり、いくつかの初期費用が必ず発生します。主に「定款認証費用」「登録免許税」「印鑑作成費用」などが挙げられ、これらは会社の形態(株式会社か合同会社か)によっても異なります。ここでは、代表的な株式会社を例に、設立時に必要な費用の内訳を解説します。
定款を紙で作成する場合、公証役場での定款認証に約5万円、登録免許税として最低15万円が必要です。加えて、印紙代2万円(電子定款なら不要)や、法人印セットの作成費用として約1万円がかかるのが一般的です。合計で概ね21万円〜25万円程度が初期コストとして見込まれます。
なお、電子定款を活用することで印紙代を節約することが可能です。電子定款は行政書士などの専門家に依頼することが多く、その際の報酬が発生しますが、トータルコストを抑えつつスムーズな設立が期待できるため、費用対効果の面で有効な選択肢といえます。
マイクロ法人を設立する際の注意点

マイクロ法人の節税効果を過度に狙いすぎると、税務署から「租税回避目的の法人」だと判断される可能性があります。たとえば、実体のない法人を設立し、収入をすべて法人に付け替えるような行為は、所得隠しと見なされる恐れがあります。また、役員報酬を極端に低く設定して保険料を抑える方法も、過去の判例では否認された事例があります。
さらに、法人と個人の経費を明確に分けていない場合や、業務実態の説明が不十分な場合にも指摘の対象となることがあります。そのため、契約書の整備や取引の記録、業務内容を裏付ける資料の保存など、実態に基づいた法人運営が必須です。
節税を目的とした法人設立は違法ではありませんが、形式的な手続きだけで実態を伴わない場合は、税務調査で否認される可能性があるため、設立後も慎重な運営が求められます。
まとめ

マイクロ法人は、社会保険料や税負担の最適化を目的として注目されている事業形態です。個人事業主とは異なり、法人格を持つことによって社会的信用度が高まり、経費として計上できる範囲が広がるなどの利点があります。
特に、一定以上の所得がある事業者にとっては、所得の分散や節税対策として有効に働く可能性があります。
しかし、マイクロ法人は誰にとっても万能な選択肢ではありません。現在の収入水準や今後の事業方針、社会保険の負担との兼ね合いを踏まえて、本当に自分にとって有益かどうかを慎重に判断することが重要です。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。