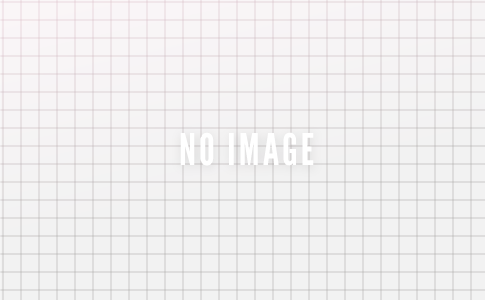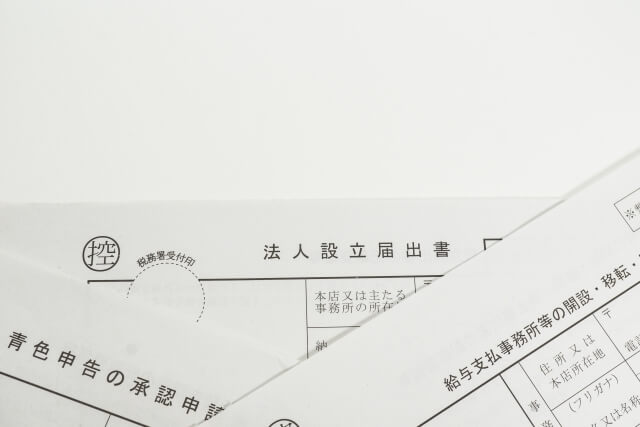<この記事は約 14 分で読めます>
会社設立前と後にやるべきことは?やることリストや費用も紹介
「会社を設立したいけど、何から手をつければいいのかわからない」「法人登記のあとに必要な手続きって、どれだけあるの?」
そんな不安を感じていませんか?
会社設立には、登記前の準備から設立後の各種届出まで、やるべきことが数多く存在します。手続きを漏らしてしまうと、罰則や業務遅延につながるリスクもあるため、正しい順序と内容を把握しておくことが大切です。
本記事では、以下のポイントを中心に、会社設立に必要な作業をわかりやすく整理しています。
- 設立前・設立後のやることリスト
- 各手続きの詳細と必要書類
- 設立にかかる費用の目安
これから会社を立ち上げようと考えている方、または準備中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
会社設立のためのやることリスト

会社を設立する際には、設立前後に対応すべき手続きや準備項目が数多く存在します。スムーズに起業を進めるためには、必要な作業をリスト化し、段階的に確認していくことが重要です。
以下に、会社設立前後でやるべきことを一覧として整理しました。
特に、法的な手続きや届出関係は漏れがあると営業開始に支障が出るため、確実に押さえておきましょう。
会社設立前にやることリスト一覧
会社設立に向けて、まずは基本的な準備を整えることが必要です。会社の方針や体制を決めたうえで、法的手続きを進めるための準備を段階的に行います。
以下は設立前に対応すべき主要な項目です。
- 会社の基本事項の決定
- 会社印の購入
- 資本金の準備
- 定款の作成と認証申請
- 法人登記
- 登記事項証明書の取得
- 印鑑カードの取得
これらの手順を順番に進めることで、正式な法人としての設立が完了します。どの工程も法的に定められているため、抜け漏れなく対応することが大切です。
会社設立後にやることリスト一覧
法人登記が完了した後も、各種行政機関への届出や手続きが必要になります。これらの手続きは、設立後一定期間内に行うことが義務づけられているため、早めの対応が求められます。
以下に主な手続きを一覧でまとめます。
- 金融機関に口座開設等の申し込み
- 税務署への届出
- 都道府県税事務所・市町村役場への届出
- 年金事務所への届出
- ハローワークへの届出
- 労働基準監督署への届出
これらの手続きは、会社の社会的責任を果たすための重要な義務です。従業員の雇用予定がある場合は、労働・社会保険関連の届出も確実に行いましょう。
会社設立前にやることリストの詳細

会社設立を円滑に進めるためには、登記前の段階で必要な準備を確実に整えることが不可欠です。このセクションでは、設立前にやるべき具体的な作業をひとつずつ解説します。
以下の項目を順に対応することで、法人登記までスムーズに到達できます。
会社の基本事項の決定
会社を設立するにあたって、まずは法人の基本方針を明確に定める必要があります。具体的には、会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金の額、役員構成、決算期などを決定します。これらはすべて定款や登記申請に記載されるため、慎重に検討しなければなりません。
特に事業目的は、将来の業務拡大を見据えて幅広く設定することが重要です。また、会社名は同一所在地での重複が認められていないため、事前に法務局の商号調査も行うと安心です。資本金の額によっては受けられる補助金や税制優遇が変わるため、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。
会社印の購入
法人登記や各種手続きには、会社印の用意が欠かせません。一般的には「代表者印」「銀行印」「角印」の3本セットで用意されることが多く、それぞれの用途に応じて使用します。代表者印は法務局に登録し、登記書類や契約書に使用される法的効力のある印鑑です。
銀行印は金融機関との口座開設時に必要となり、角印は社内文書や請求書に押印されるものです。印影は法人の“顔”ともいえるため、信頼性や視認性を考慮し、適切な書体やサイズを選ぶと良いでしょう。インターネットや印鑑店で数千円〜1万円前後で作成可能です。
資本金の準備
資本金とは、設立時に会社に出資されるお金のことで、設立後の事業運営に使われる基本的な資金です。株式会社や合同会社などの形態にかかわらず、1円以上で設立可能ですが、信用力や融資審査、税務の観点からある程度の金額を用意しておくのが一般的です。
出資金は、会社設立時の代表者個人名義の銀行口座に振り込む形で準備します。設立後に法人口座へ資金を移す際の記録(振込明細や通帳コピー、ネットバンクの場合は金融機関情報や口座情報、入金日や入金額がわかるページ)は登記時の証明資料として提出が必要です。また、複数名で出資する場合は、出資比率や持株比率の決定も併せて行いましょう。
定款の作成と認証申請
定款は、会社の基本的なルールや構成を定めた文書で、設立時に必ず作成し、公証役場での認証を受ける必要があります(合同会社は認証不要)。定款には、商号・目的・所在地・資本金・機関設計などを記載します。
電子定款を作成する場合は印紙税4万円が不要になるため、コスト削減の面で有利です。作成後は、公証人による内容確認と署名・押印を経て、PDF形式で認証済定款を受け取ります。なお、公証役場の予約は混雑することがあるため、早めのスケジュール調整が望ましいです。
法人登記
法人登記は、会社を法的に設立するために必要な手続きです。登記をもって法人格が発生し、正式に会社として認められます。登記申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局で行い、定款、登記申請書、出資証明書などの添付書類が必要です。
申請日をもって会社の設立日となるため、希望する日付に合わせて準備を進めることが可能です。登記手数料として登録免許税(株式会社は15万円、合同会社は6万円)が発生します。提出後、登記完了までには通常1週間程度かかります。
登記事項証明書の取得
登記が完了すると、会社情報が法務局に登録され、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得できるようになります。この書類は、銀行口座開設や各種届出の際に必要となるため、複数部を準備しておくと便利です。
証明書は法務局の窓口、郵送、またはオンライン申請で取得可能です。1通あたり600円(オンライン交付を郵送で受け取る場合は520円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合は490円)で取得でき、設立初期は3~5通程度用意しておくと安心です。なお、変更登記が発生した場合は、再度取得が必要になります。
印鑑カードの取得
印鑑カードは、法務局で印鑑証明書を発行する際に必要なカードで、会社設立時に法務局に登録した代表者印に対応する証明手段です。登記完了後に、法人の代表者が法務局で申請し、即日または数日以内に受け取ることができます。
印鑑証明書は、銀行との取引や不動産契約、重要な法的文書において使用されるため、印鑑カードの取得は速やかに行うことが求められます。証明書の発行には印鑑カードが必須となるため、紛失や盗難時には速やかな再発行手続きも必要です。
会社設立後にやることリストの詳細

法人登記が完了した後も、会社を適切に運営し、法的義務を果たすために複数の届出を行う必要があります。
これらの手続きは、税務・労務・社会保険など多岐にわたり、所定の期限内に対応しなければ罰則や不利益を被る可能性もあります。
金融機関に口座開設等の申し込み
法人名義の銀行口座を開設するには、登記完了後に必要書類をそろえて金融機関に届け出る必要があります。基本的に求められるのは、登記事項証明書、印鑑証明書、定款、印鑑(銀行印)などです。
法人設立直後は、金融機関によって審査が厳しいケースもあるため、取引実績や事業計画書を提出して口座開設の目的を明確にすることが重要です。ネットバンクや都市銀行、地方銀行によって開設の条件や対応速度が異なるため、複数行での検討も効果的です。
税務署への届出
会社設立後には、税務署へ各種書類を提出する義務があります。主なものとしては、「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などがあり、会社設立後原則2ヶ月以内に提出が必要です。
これらの届出を怠ると、青色申告による節税メリットを受けられなかったり、税務処理が煩雑になったりするリスクがあります。書類の記入には正確性が求められるため、税理士など専門家への確認も有効です。
都道府県税事務所・市町村役場への届出
法人住民税・法人事業税に関する手続きとして、都道府県税事務所および市区町村役場への法人設立届出が必要です。この届出は、会社設立後1ヶ月以内を提出期限としている自治体が多く、税務署への届出とは別に行う点に注意が必要です。
都道府県、市町村への設立届には登記事項証明書と定款のいずれも必要です。自治体ごとに様式や提出方法が異なるため、事前に各自治体の公式サイトで確認しておくとスムーズです。
年金事務所への届出
従業員を1人でも雇用する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所となるため、日本年金機構の年金事務所への届出が必要です。主な提出書類は、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「被保険者資格取得届」などです。
これらの書類は、会社設立日または雇用開始日から5日以内に提出する必要があり、提出が遅れると保険給付や労使トラブルの原因となります。あわせて保険料の支払いスケジュールも把握しておくことが重要です。
労働基準監督署への届出
労働者を雇用する会社は、労働基準法に基づき労働基準監督署への届出を行う義務があります。主な書類として、「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」「就業規則(常時10人以上の場合)」などがあります。
届出は、雇用開始後10日以内が目安となっており、労災保険加入や法定労働条件の整備のために必要な手続きです。特に建設業など労災リスクが高い業種では、提出漏れがあると重大な問題に発展するため注意が必要です。
ハローワークへの届出
従業員を雇う場合は、雇用保険の適用事業所としてハローワークへの届出が義務付けられています。「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」などを、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
届出期限は、雇用開始日から10日以内です。雇用保険は失業給付や助成金制度とも連動しているため、未加入は従業員の不利益につながる可能性があります。雇用保険番号の取得は、労務管理においても基本的なステップとなります。
会社設立に必要な費用

会社設立には、登記費用や印鑑代、専門家報酬など、さまざまな初期コストが発生します。設立形態(株式会社・合同会社)や手続きを代行するかどうかによって、必要な金額は変動しますが、一般的な目安は以下のとおりです。
まず、株式会社を設立する場合は、登録免許税が15万円、定款認証費用は資本金の額等に応じて3~5万円、印紙税が4万円(電子定款なら不要)かかります。一方、合同会社であれば定款認証が不要で、登録免許税は6万円と比較的安価です。
これに加えて、印鑑作成費用や登記事項証明書の取得費用、印鑑証明書の発行費用も数千円単位で必要です。
事前に見積もりを立て、設立後の運転資金に支障が出ないように資金計画を立てておくことが重要です。
まとめ

会社設立は、夢やビジョンを形にする第一歩であり、慎重かつ計画的に進める必要があります。設立前には、会社の基本事項の決定から法人登記に至るまで、法的な手続きや書類準備が求められます。登記完了後も、税務署や自治体、社会保険関連機関への届出を怠らないことが重要です。
こうした手続きを正確にこなすことで、事業の土台が安定し、安心して経営に集中できる環境が整います。特に、期限が定められている届出は、設立後のスケジュールに組み込み、早めに対応することが求められます。
設立に必要な費用も事前に把握し、資金繰りや経費計上を計画的に行うことが、スムーズな起業の鍵となります。今後の事業成長を支えるためにも、初期段階から法務・労務・税務の管理体制を整えておくことが成功への第一歩です。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。