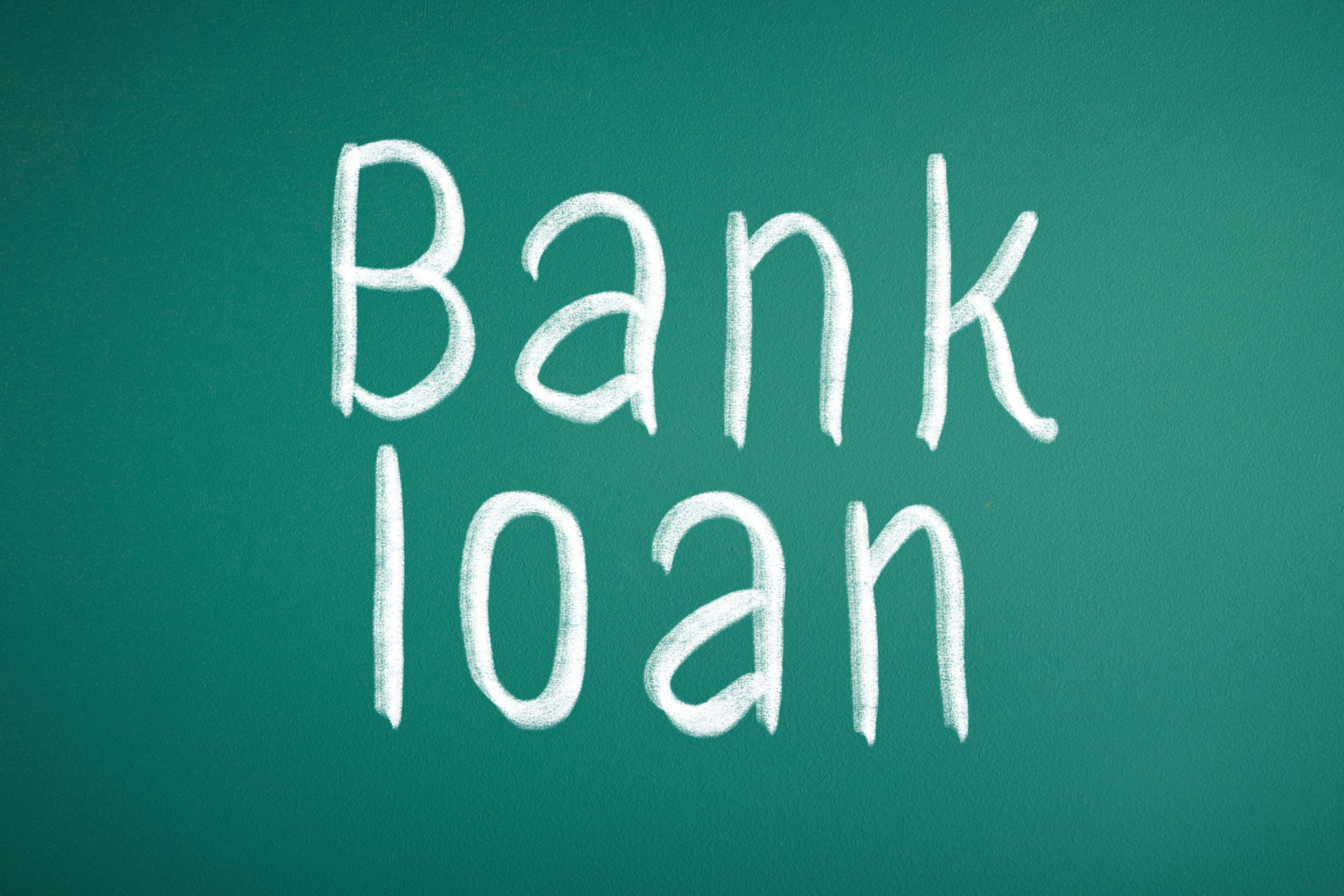<この記事は約 15 分で読めます>
「節税目的で投資会社を作ったほうがいいって聞くけど、実際どうなの?」「副業で投資してるけど、法人化のタイミングが分からない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
投資会社の設立には、税制上の優遇や経費処理の柔軟性、資産管理の明確化など多くの利点があります。一方で、社会保険料や事務負担、設立コストといったデメリットも無視できません。法人化は正しくタイミングを見極めることで、その効果を最大化できます。
本記事では以下の点をわかりやすく解説します。
- 投資会社を設立するメリット・デメリット
- 法人化が向いている投資家のタイプとタイミング
- 設立手順と注意点
投資活動の次の一手として「法人化」を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
投資会社とは

投資会社とは、株式・不動産・債券などへの資産運用を目的として設立される法人のことです。個人投資家が自らの資産を法人を通じて運用するケースが多く、いわゆる「資産管理会社」とも呼ばれます。法人化することで節税や経費計上の自由度向上、資産の分散管理などが可能になり、長期的な資産形成に有利な仕組みを構築できます。
なお、「投資会社」という会社形態が法律上に明確に存在するわけではなく、株式会社や合同会社といった一般的な法人形態を用いて設立されます。あくまで「投資を主目的とする会社」を通称的に投資会社と呼んでいます。
個人投資家が投資会社を設立する5つのメリット

投資会社を設立することで、個人投資家は以下の5つの大きなメリットを享受できます。
- 節税効果が期待できる
- 経費として計上できるものが増える
- 所得の分散が可能になる
- 赤字の繰り越しができる
- 社会的な信用度が向上する
それぞれの内容について、以下で詳しく解説します。
節税効果が期待できる
投資会社を設立する最大のメリットの一つが節税効果です。法人税率は所得が一定以上になると個人より低くなり、特に課税所得が900万円を超えるような投資家にとっては有利です。また、所得税の累進課税を避けることで、税負担を軽減しながら利益を手元に残すことが可能になります。
さらに、法人に利益を留保することで、次年度以降の投資資金として効率的に活用できます。
経費として計上できるものが増える
法人化することで、個人事業主では扱いにくい経費や制度的に認められにくい支出を会社経費として処理できるようになります。代表的なものとして、以下が挙げられます。
- 社会保険料の法人負担分
- 法人契約による生命保険料
- 出張時の旅費日当
- 社宅家賃の一部負担
- 役員報酬や退職金
これらは法人ならではの制度や会計処理を通じて経費化できるため、課税所得を効果的に圧縮し、結果として税負担を下げることにつながります。
もちろん、業務実態や合理性が伴っていることが前提であり、過度な経費計上は税務上のリスクを伴う点には注意が必要です。
所得の分散が可能になる
法人を設立することで、配偶者や親族を役員や従業員として登用し、実際に事業へ従事した労務の対価として役員報酬や給与を支払うことが可能になります。これにより、家族全体での所得を分散させ、結果として税負担を軽減できるケースがあります。
特に高所得者で個人の税率が高い場合には、所得分散による節税メリットが大きくなる可能性があります。ただし、形式的に給与を支給するだけでは認められず、実際の業務内容や合理的な金額設定が必要である点には注意が必要です。
赤字の繰り越しができる
法人は、損失(赤字)を最大10年間にわたって繰り越すことが可能です。一方、個人では繰り越し期間は3年です。長期的な投資計画を考える場合には法人の方が柔軟な損益管理ができます。
たとえば不動産投資で初年度に大きな支出が発生した場合でも、将来の黒字に充てて税負担を抑えることが可能です。
社会的な信用度が向上する
法人を持つことで、社会的な信用力が高まるというメリットもあります。たとえば、銀行融資を受けやすくなる、名刺やWebサイトに法人名義を記載できるなど、対外的な信頼性が向上し、取引や資金調達の幅が広がる可能性があります。
これは、投資以外の事業展開や不動産取得の場面でもプラスに働きます。
個人投資家が投資会社を設立する3つのデメリット

投資会社の設立には多くの利点がありますが、その一方で無視できないデメリットも存在します。ここでは、個人投資家が法人化を検討する際に注意すべき3つの課題を詳しく解説します。
- 会社の設立費用や維持費がかかる
- 社会保険料の負担が必要になる
- 事務処理が増える
会社の設立費用や維持費がかかる
投資会社を設立するには、定款認証や法人登記などにかかる初期費用が発生します。たとえば株式会社の場合、登録免許税や定款認証料を含めて約20万円前後が必要です。
また、法人設立後も、毎年の決算申告に伴う税理士報酬や、会社維持のための会計ソフト利用料、法人口座の維持手数料など、さまざまな固定的なランニングコストが発生します。
これらの費用は、一定規模の利益が継続して出ていない投資家にとっては負担となりやすく、節税効果を上回ってしまう可能性もあるため注意が必要です。
社会保険料の負担が必要になる
投資会社を設立し、自らに役員報酬を設定した場合、健康保険や厚生年金などの社会保険への加入義務が生じます。社会保険料は報酬額に応じて毎月発生し、年間で数十万円以上になることも珍しくありません。
個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金への加入が基本となり、これらは任意性や負担額の幅があります。一方、法人化すると社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則義務となり、保険料は会社と役員・従業員が折半で負担する仕組みに変わります。
そのため、表面的には個人の負担は軽減されますが、会社側で同額を負担する必要があるため、法人全体としてのコストは高くなりやすい傾向があります。特に役員報酬を高く設定する場合、社会保険料の総額も増えるため、資金計画に組み込んでおくことが重要です。
事務処理が増える
法人を運営する上では、多くの事務的な手続きや報告義務が伴います。たとえば、会計帳簿の作成、法人税や消費税の申告、源泉徴収、年末調整、社会保険関連の届出など、煩雑な業務が日常的に発生することになります。
自分で行うことも可能ですが、専門知識がない場合は税理士や社労士に依頼することが一般的であり、その分の外注コストも必要になります。
投資に集中したい方にとっては、事務作業の煩雑さがパフォーマンス低下の要因になる恐れもあるため、事前に体制を整えておくことが重要です。
投資会社を設立すべき投資家の例

すべての個人投資家にとって投資会社の設立が最適とは限りません。ここでは、法人化によるメリットを享受しやすい具体的な投資家のタイプを紹介します。
- 個人投資家
- 資産運用をおこなうサラリーマン
- 相続税の発生が見込まれる投資家
- オーナー社長
個人投資家
継続的に株式や不動産、暗号資産などで利益を上げている個人投資家は、投資会社を設立することで節税や資産管理の効率化が図れます。特に年間の課税所得が900万円を超える水準に達している場合は、累進課税による高い税率を回避し、法人税率の恩恵を受けることで手元に残る利益を増やすことが可能です。
加えて、損失の繰り越しや経費計上の柔軟性も法人の方が有利であり、長期的に資産を築きたい個人投資家にとって、法人化は非常に有効な手段となります。
資産運用をおこなうサラリーマン
給与所得に加えて副業的に投資を行っているサラリーマンにとっても、投資会社の設立は有効な選択肢です。たとえば、不動産収入や株式配当などの副収入が増加している場合、法人を設立してそれらを受け皿にすることで、所得を分離し節税効果を高めることができます。
また、法人名義で投資を行うことで、プライベート資産との切り分けが明確になり、資金管理や損益の把握がしやすくなるというメリットもあります。会社員としての信用力を活かして法人の融資を受けることも可能です。
相続税の発生が見込まれる投資家
将来的に相続税の課税対象となる資産を保有している投資家にとって、法人化は有効な相続対策となります。法人で不動産などの資産を保有する場合、相続時には株式という形での評価となり、相続評価額が圧縮される可能性があります。
また、相続人が法人の株式を引き継ぐ形であれば、資産の分割がしやすく、争族リスクの軽減にもつながります。このように、税額の最小化と資産継承の円滑化を両立できる点は、法人化の大きな魅力です。
オーナー社長
既に事業会社を経営しているオーナー社長にとっては、余剰資金の運用先として投資会社を設立することが合理的な選択肢となります。本業とは切り分けた形で法人を持つことで、利益の分散やグループ経営による税務戦略の幅が広がるからです。
また、投資活動を明確に分離することで、資金の流れや管理責任が明瞭になり、監査対応や会計処理の正確性も確保しやすくなります。将来的な事業承継や資産移転の観点からも有利です。
個人投資家が投資会社を設立すべきタイミング

投資会社の設立は、単なる思いつきや節税目的だけで判断するものではありません。税負担・投資収益・将来的な資産形成などを総合的に見極め、法人化のメリットがデメリットを上回る時期を見極めることが重要です。特に以下のような状況は、設立を検討する目安となります。
たとえば、課税所得が年間900万円を超えた場合、個人の税負担は所得税33%に住民税10%が加わり、合計で43%以上に達します。一方で法人の場合は、法人税・地方法人税・法人住民税・事業税などを合わせた法定実効税率が30〜33%程度で推移しており、この差が大きくなる段階で法人化による節税効果が現実的になります。
また、不動産投資における減価償却や初期費用が多く発生するタイミングでは、赤字繰越や経費処理の柔軟性を活かせる点も法人化の利点です。
ただし、設立費用や維持コスト、社会保険料の負担といった固定費も発生するため、収益が安定していない段階では慎重な判断が求められます。
投資会社を設立する流れ

投資会社の設立には、一般的な法人設立と同様の手続きが必要です。以下の3ステップを順に実施することで、法的に適正な会社として登記が完了します。
- 会社の基本項目を決める
- 定款を作成して公証役場で認証申請をする
- 必要な書類を用意して登記申請する
会社の基本項目を決める
最初のステップは、会社の基本情報を明確にすることです。具体的には、会社の商号(名前)、所在地、資本金、発起人・役員の構成、事業目的などを決定します。特に「事業目的」については、投資活動を主とする旨を明記する必要があります(例:「不動産の取得・保有・賃貸」「有価証券の保有・運用」など)。
また、法人形態としては設立コストや運営の柔軟性を考慮して、合同会社(LLC)が選ばれるケースも増えています。この段階での設計が、その後の登記や税務にも影響を与えるため、専門家の助言を受けながら慎重に決めることが推奨されます。
定款を作成して公証役場で認証申請をする
株式会社を設立する場合、定款(会社の基本ルール)を作成し、公証役場での認証を受ける必要があります。定款には、商号・目的・所在地・設立に関する出資の内容などが記載されます。定款の認証手数料は5万円、印紙代が4万円(電子定款の場合は免除)など、ここで一定の設立コストが発生します。
合同会社の場合は公証人の認証が不要なため、この工程は省略可能です。認証を受けた定款は、以降の登記手続きで必要になるため、原本とコピーを適切に保管しておきましょう。
必要な書類を用意して登記申請する
定款の認証が完了したら、法務局へ法人設立の登記申請を行います。必要書類としては、設立登記申請書、定款、設立時取締役の印鑑証明書、就任承諾書、資本金の払込証明書、印鑑届出書などがあります。提出は会社の本店所在地を管轄する法務局で行い、申請日が登記上の「設立日」となります。
登録免許税として、株式会社は資本金の0.7%(最低15万円)、合同会社は資本金の0.7%または6万円のいずれかの高い金額がかかります。提出後、法務局の審査を経て、登記が完了すれば法人設立となり、晴れて投資会社として活動を開始できます。
まとめ

投資会社の設立は、節税や資産管理の効率化、信用力の向上など多くのメリットがある一方で、設立費用や社会保険料、事務負担といったデメリットも伴います。そのため、法人化は「何となく」ではなく、投資収益の規模や今後の資産形成、相続対策などを踏まえた中長期的な視点で判断することが重要です。
特に、年間の課税所得が900万円を超えた投資家や、不動産など複数の資産を保有する層、将来の相続を見据えた方には法人化のメリットが大きくなります。設立手続きや税務処理には専門知識が必要となるため、税理士などの専門家と連携しながら準備を進めることが成功のカギです。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。