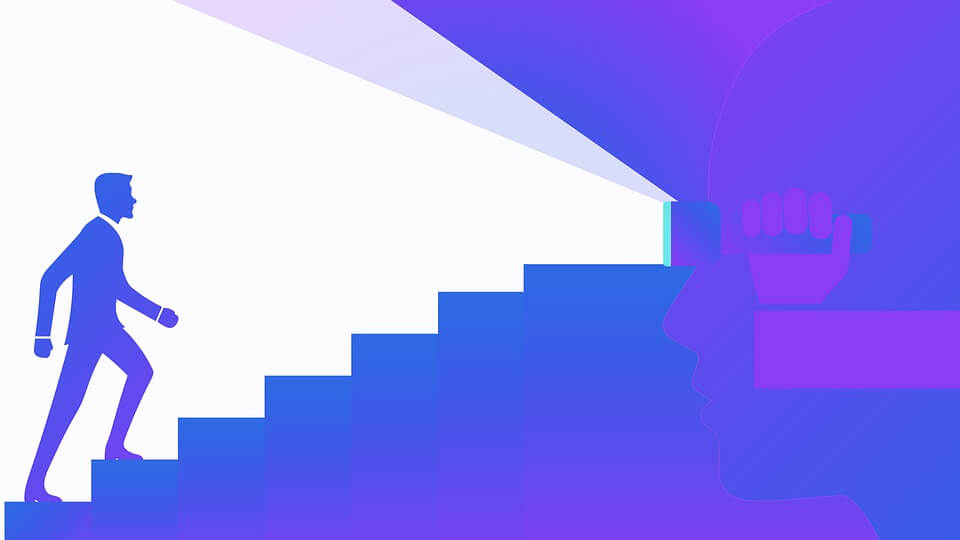<この記事は約 18 分で読めます>
「一人で会社を作ってみたいけど、手続きが複雑そう…」「個人事業主のままと法人化、どちらがいいの?」
そんな不安や疑問を感じていませんか?
個人会社の設立は、社会的信用の向上や節税メリットが期待できる一方で、手続き・税金・社会保険など、押さえるべきポイントも多く存在します。準備不足のまま進めてしまうと、余計なコストやリスクを背負う可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、以下の6つの観点から、個人会社の設立を検討する方に必要な情報を分かりやすく解説します。
- 一人で作れる会社の形態とは
- 一人会社と個人事業主の違い
- 一人で会社設立する手順
- 一人会社のメリット
- 一人会社のデメリット
- 設立時の注意点
法人化を検討している個人事業主やフリーランスの方は、ぜひ最後までご覧ください。
一人で作れる会社の形態とは
 個人で会社を設立する場合、主に「株式会社」または「合同会社(LLC)」のいずれかを選択できます。
個人で会社を設立する場合、主に「株式会社」または「合同会社(LLC)」のいずれかを選択できます。
株式会社は社会的信用度が高く、融資や取引の面で有利な一方で、設立費用や書類の手間が大きい傾向があります。合同会社は費用が安く、意思決定がスムーズな反面、知名度や外部評価に差が出る場合があります。
いずれの形態にもメリット・デメリットがあるため、事業の規模や目的に応じて適切な選択を行うことが重要です。
一人会社と個人事業主の違い

個人で事業を始める際、「法人として会社を設立するか」「個人事業主として始めるか」で迷う人は多いでしょう。ここでは、以下の5つの観点から違いを比較します。
- 社会的な信用
- 課される税金
- 立ち上げ時の手続きや費用
- 責任の範囲
- 経費の幅
これらを理解しておくことで、自身の事業に最も適した形態を判断できるようになります。
社会的な信用
一般的に、会社設立によって法人化した事業は、個人事業主よりも社会的信用が高いとされます。取引先や金融機関、自治体、採用候補者に対して「法人格を持っていること」が信頼性の証となり、営業活動や資金調達において有利に働くケースが多くあります。
特に、BtoBのビジネスを行う場合や、大手企業と取引を目指す場合には、会社組織であることが前提条件となる場合もあります。
一方、個人事業主は柔軟性が高い反面、取引先によっては規模や信頼性を理由に、契約に至りにくいケースがある点に注意が必要です。
課される税金
税金面では、課税の対象や計算方法に大きな違いがあります。個人事業主の場合、所得に応じて超過累進課税が適用され、所得が増えるほど税率が上がります(最大45%)。
一方、法人は一定の法人税率が適用され、利益が高くなるほど節税効果が出やすくなる傾向があります。また、法人の場合は「役員報酬」として自分に給与を支払えるため、所得分散による節税も可能です。
消費税や住民税の取り扱いにも差があるため、年間の収益見込みをもとに事前に試算しておくとよいでしょう。
立ち上げ時の手続きや費用
立ち上げにかかる手続きや費用にも違いがあります。個人事業主は開業届の提出と青色申告の承認申請のみで開始可能であり、費用はほとんどかかりません。
一方、法人設立には登記が必要で、株式会社なら約20万円前後、合同会社でも約6万円程度の初期コストがかかります。
また、法人は定款の作成・認証や、印鑑の登録、銀行口座の開設など、準備する書類やステップも多く、開業までのリードタイムも長くなりがちです。気軽に始めたいなら個人事業、制度や信頼性を重視するなら法人が選ばれる傾向にあります。
責任の範囲
個人事業主は無限責任を負い、事業で負った負債は個人資産を使ってでも返済する義務があります。つまり、トラブル時に家や貯金など私有財産を差し押さえられるリスクがあります。
一方、法人(株式会社・合同会社)は有限責任のため、出資金の範囲でしか責任を負いません。会社が倒産しても原則として個人資産は保護されます。ビジネス規模が大きくなるほど重要になり、長期的なリスク管理を考えるうえでも無視できない要素です。
経費の幅
法人化すると、経費として計上できる範囲が広がるという利点があります。たとえば、社宅制度を活用することで家賃の一部を経費にできたり、出張手当や役員報酬の調整など、柔軟な資金管理が可能になります。また、交際費や福利厚生費の扱いも、法人の方が制度的に整っており、節税効果の高い運用が実現しやすいのが特徴です。
一方、個人事業主は経費の範囲に一定の制約があり、プライベートとの区別が難しい費用は除外されがちです。事業内容によっては、この点が経営の柔軟性に影響を及ぼす場合もあります。
一人で会社設立する手順

会社設立は、次の5つのステップに沿って進めることで、スムーズに手続きを完了できます。
- 会社の基本事項を決める
- 法人用の印鑑を作る
- 定款を作成して認証を受ける
- 資本金を払い込む
- 登記申請書類を作成し、法務局で申請する
各工程には、必要書類の準備や法的な決まりがあるため、順序を守って確実に進めることが重要です。
会社の基本事項を決める
会社設立の第一歩は、商号(会社名)・所在地・目的(事業内容)・資本金・決算期など、会社の基本事項を明確に決めることです。これらの内容は定款に反映されるため、後から変更するには手間と費用がかかります。
特に「商号」は同一住所で同一名称が使えないため、事前に法務局の商号調査を行うことが推奨されます。また、目的欄には将来的に行う予定の事業も幅広く記載しておくと、後の変更申請が不要になり手間を省けます。
法人用の印鑑を作る
登記や銀行口座の開設に必要なため、会社名義の印鑑を作成します。一般的には「代表者印(実印)」「銀行印」「角印」の3種類を用意するのが通例です。特に「代表者印」は法務局に届け出る重要な印鑑で、登記書類や契約書などあらゆる場面で使われます。
印鑑の作成は印鑑業者やネット注文でも対応可能で、届出用の印影サイズや素材の選定にも注意が必要です。印鑑証明カードの発行は、後述の登記申請に不可欠となるため、余裕を持って準備しましょう。
定款を作成して認証を受ける
定款は会社の憲法ともいえる重要な書類で、会社の目的・組織・機関・決算期などを明記します。株式会社を設立する場合は、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。紙の定款では印紙税4万円が課されますが、電子定款なら非課税となるため、コスト削減の面でも電子化が推奨されます。
認証には、事前予約・必要書類の準備・本人確認など複数の手続きがあり、時間に余裕を持つことが望ましいです。合同会社の場合、定款認証は不要ですが、内容の整合性が後の登記に関わるため、専門家にチェックしてもらうのが確実です。
資本金を払い込む
定款の認証が完了したら、設立する会社の資本金を、発起人個人の銀行口座に一時的に払い込む必要があります。この口座は発起人個人名義で問題ありませんが、「会社名義の口座」はまだ存在しないため、通帳の写しや入金明細をもとに払い込み証明書を作成します。
資本金は1円からでも設立可能ですが、金融機関との信頼関係や取引先の評価を考慮すると、ある程度の額を設定するケースが一般的です。資本金の払込後は、登記書類の作成と登記手続きに進みます。
登記申請書類を作成し、法務局で申請する
最後に、法務局への登記申請が必要です。申請書のほか、定款、印鑑届出書、資本金の払込証明、役員就任承諾書などの書類を一式揃える必要があります。書類に不備があると差し戻しとなるため、事前のチェックが重要です。
登記申請は原則として管轄の法務局に書面で提出しますが、近年はオンライン申請にも対応しており、マイナンバーカードや電子署名を活用すれば郵送不要で手続きが完了します。申請後、問題がなければ通常1週間程度で登記が完了し、会社が正式に成立します。
一人で会社を作るメリット

一人会社を設立することで得られる代表的なメリットは、以下の4つです。
- スムーズな意思決定ができる
- 法人化の際に必要な費用が抑えられる
- 経営に必要な知識が得られる
- 働き方を自由に選べる
個人で事業を行う自由度と、法人格の持つ制度的メリットを両立させられる点が一人会社の魅力です。
スムーズな意思決定ができる
一人会社では、すべての経営判断を自分ひとりで行えるため、会議や承認プロセスを経る必要がなく、スピーディな意思決定が可能です。これは特に、小規模なスタートアップやフリーランス型ビジネスにおいて大きな強みとなります。
市場の変化に即応した対応ができるため、タイムロスによるビジネスチャンスの逸失を防げます。また、他人の意見に左右されることなく、自身のビジョンをそのまま事業に反映させることができる点も、一人会社ならではのメリットといえるでしょう。
法人化の際に必要な費用が抑えられる
複数人で会社を設立する場合、役員報酬の分配や会議体制の整備など、人的コストや運営管理コストがかかりやすくなります。一方、一人会社ではそうしたコストがかからず、必要最低限の手続きと費用で運営が可能です。
たとえば、合同会社であれば登記時の登録免許税は6万円からと低く抑えられ、定款の認証も不要です。創業初期において資金繰りに余裕を持たせる大きな要因となり、事業の継続率にも良い影響を与えることがあります。
経営に必要な知識が得られる
一人会社を運営する過程では、会計・税務・契約・労務など幅広い実務を自分で把握する必要があるため、自然と経営に関する実践的な知識が身につきます。これは将来的に組織を拡大したり、他人を雇用するフェーズに進んだときに大きな財産となります。
初期の段階で業務の仕組みやリスク管理、資金繰りの考え方を習得しておくことで、経営者としての視野が広がり、長期的なビジネス展開に強くなるのです。自分自身を「学びながら成長させる場」として活用できる点が、一人会社の醍醐味ともいえるでしょう。
働き方を自由に選べる
会社員時代と異なり、一人会社では働く時間・場所・進め方をすべて自分で決めることが可能です。ライフスタイルに合わせた柔軟なスケジュールが組めるため、育児・介護・副業などとの両立も実現しやすくなります。
また、オフィスを持たずリモートで事業を展開するなど、固定費の最小化と自由な働き方の両立ができる点も大きな魅力です。現代ではオンライン商談・クラウドツールの普及により、個人でも全国・全世界と取引ができる時代。働き方の選択肢は大きく広がっています。
一人で会社を作るデメリット

一人会社には多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットや負担も存在します。
- すべての手続きを自分でする必要がある
- 自分の能力だけですべてが決まる
- 一人だけだと信用度がそこまで高くない
法人化の前に、こうしたリスクや負荷も冷静に理解し、事業継続に耐えうる体制かどうかを見極めることが大切です。
すべての手続きを自分でする必要がある
一人会社では、会社設立の準備から、登記、税務申告、口座開設、社会保険手続き、契約管理など、すべてを自分ひとりで対応する必要があります。特に設立初期は対応する業務範囲が広く、専門用語や制度を学びながら進めるため、想定以上に時間と労力がかかることもあります。
外注や顧問の活用によって一部は負担軽減できますが、それにもコストが発生するため、すべてを自力でやると消耗しやすいのが実情です。作業に追われ、本業に集中できないケースも少なくありません。
自分の能力だけですべてが決まる
経営・営業・実務・経理・法務など、会社運営に必要な意思決定や実行はすべて自分のスキルと経験に委ねられます。つまり、自分が動かなければ事業は進まず、自分の弱点がそのまま事業の成長を妨げるリスクにもなります。
相談できるパートナーがいないため、孤独感や不安を抱えながら意思決定を迫られる場面もあるでしょう。特に初期段階では、仕事の進め方や方向性に迷いが生じやすく、モチベーションの維持も課題となります。
一人だけだと信用度がそこまで高くない
法人化すればある程度の社会的信用は得られますが、「経営陣が自分1人だけ」という状況は、組織としての安定性や継続性に対する懸念を持たれることもあります。特に、融資審査や業務委託の場面では「1人で運営している会社」という点が慎重な評価の対象となりがちです。
実績が浅いうちは、信頼を勝ち取るために通常以上の丁寧な説明や交渉が必要になるケースもあります。法人だからといって信用が自動的に得られるわけではない点は注意が必要です。
一人で会社を設立する際の注意点

一人会社の設立には大きな自由と裁量がありますが、制度上の義務や見落としがちなリスクにも注意が必要です。特に以下の4点を事前に確認しておきましょう。
- 健康保険と厚生年金保険への加入が必須になる
- 経費の扱いに気を付ける
- 役員報酬で税金が変わる
- 個人事業主の名義は廃業手続きが必要になる
正しく準備することで、将来的なトラブルや過剰な税負担を防ぐことができます。
健康保険と厚生年金保険への加入が必須になる
法人を設立すると、たとえ役員1人だけの会社であっても健康保険と厚生年金への加入が法律で義務付けられます。これは従業員がいない場合でも例外ではありません。
社会保険料の負担は、個人事業主時代の国民健康保険・国民年金と比べて高くなるケースが多く、会社と個人がそれぞれ半額ずつを負担します。このため、報酬の設定やキャッシュフローに与える影響が大きくなる点には特に注意が必要です。
経費の扱いに気を付ける
法人と個人の支出は明確に分ける必要があり、プライベートな支出を会社の経費として計上することは認められていません。違反すれば税務調査で否認され、追徴課税のリスクを招きます。
たとえば、飲食代・交通費・備品購入などの支出についても、「業務に必要なものであること」を証明できるよう領収書や記録を残すことが重要です。個人事業と異なり、会社の経費として処理できる幅は広がる一方、社用・私用の線引きをあいまいにしてしまうと、逆にリスクも増えることになります。
役員報酬で税金が変わる
法人では、代表者である自分に対して「役員報酬」を支払うことで、給与所得として所得税の計算が行われます。この役員報酬の額は、毎期の決算で設定し、原則として事業年度内に変更できないというルールがあります。
金額が高すぎれば社会保険料や所得税の負担が重くなり、低すぎれば会社に利益が残って法人税が増えるという、バランスが重要な項目です。利益予測や資金繰りを踏まえて適切な額を設定し、税理士など専門家に事前相談することが推奨されます。
個人事業主の名義は廃業手続きが必要になる
個人事業主として開業届を提出済みで、そこから法人成り(会社設立)する場合は、旧名義の「廃業届」を税務署に提出するのがおすすめです。この手続きを行わずにいると、税務上「個人事業と法人が同時に存在している」状態と見なされ、確定申告や青色申告などで混乱を招く可能性があります。
あわせて、事業用口座や契約の名義変更も進めておくとよいでしょう。移行タイミングを明確にし、書類上も整理することが大切です。
まとめ

一人で会社を設立するという選択は、個人事業主にはない制度的なメリットや社会的信用を得られる反面、一定の責任と負担も伴います。法人化することで節税の選択肢が広がり、経費処理や信用面でも有利になりますが、設立費用や社会保険の義務といった初期コストは避けられません。
会社の形態としては、株式会社や合同会社などがあり、それぞれ設立手続きや信用度に違いがあります。また、法人と個人事業主の違いは、税金、責任の範囲、経費の使い方にまで及びます。
判断に迷う場合は、税理士や専門家に相談しながら、納得のいく形でのスタートを切ることをおすすめします。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。