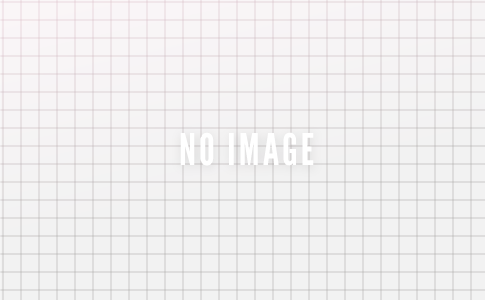<この記事は約 17 分で読めます>
身の回りの人から金銭などの資産を受け取る場合、額に応じて税金が発生します。
代表的なのが相続税と贈与税の2つです。これらの税金は、受け取り方によって金額を大幅に抑えられます。
この記事では以下2つについて解説します。
- 相続税と贈与税の違い
- 相続と生前贈与はどちらが得するか?
- 相続税・贈与税を選ぶべきケース
相続税と贈与税について理解できれば、より多くのお金を大切な人に残せるため、ぜひご一読ください。
相続税と贈与税の違い

相続税と贈与税の違いを解説します。
相続税とは
相続税とはある人の財産・権利を相続したときに発生する税金のことです。
受け取れるのは法定相続人で、亡くなった人の配偶者や子どもなどが該当します。
相続税の対象となる財産・権利には以下のようなものがあります。
- 現預金
- 有価証券
- 不動産
- 保険金(死亡保険金・損害保険金等)
- 借金・未払金
- 保証人・連帯保証人の地位
相続の際の注意点として、相続をすると借金や連帯保証人の地位など「負の資産」まで引き継がれてしまうことです。
また、相続税は相続した全額に課せられるわけではなく、以下の計算式で算出される「基礎控除額」を上回る部分に課税されます。
【基礎控除額の計算式】
・相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人×600万円
【関連】相続税の基礎控除とは?計算方法、注意点もあわせて解説
なお、相続税の税率は以下のように決められています。
| 課税対象額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
親や配偶者が亡くなったときに相続した資産に対して、上記の税率をもとに相続税が算出されます。
贈与税とは
贈与税とは人から住居や金銭などの資産をもらったときに発生する税金です。
親や祖父母など身内から受け取るのが一般的ですが、気心の知れた血縁関係のない人から受け取るケースもあるでしょう。
相続税に比べると高い税率が掛かってしまいますが、生前贈与をうまく活用すれば非課税、もしくは最小限の納税で資産を受け取れることもあります。
贈与税の税率は以下のように決められており、相続税に比べると高めに設定されています。
| 課税対象額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※特例贈与財産用の場合
基礎控除額は受取人1人につき年間110万円までと決められており、それを上回る場合は上記の税率に沿って贈与税が掛かります。
それ以外にも後述する特例・控除の制度を活用すれば、より多くの財産を非課税での贈与も可能です。
ただし、贈与者の死亡から遡って3年以内に生前贈与が行われたものに関しては、相続税がかかります。
相続税と贈与税の比較一覧表
相続税と贈与税の主な違いは、以下に比較表をご参照ください。
| 相続税 | 贈与税 | |
| 課税されるタイミング | 遺産を相続したとき | 個人から資産をもらったとき |
| 納税者 | 相続人 | 受贈者 |
| 基礎控除額 | 3,000万円+法定相続人数×600万円 | 受贈者1人につき年間110万円 |
| 最低税率 | 10% (1,000万円以下) | 10% (200万円以下) |
| 最高税率 | 55% (6億円超) | 55% (4,500万円超) |
相続税の方が基礎控除額が高い上に税率も低いため、相続に回した方がお得に見えます。
しかし、生前贈与を上手に活用すれば非課税もしくは相続税以下の税額で抑えられることもあります。
相続と生前贈与はどちらが損する?得する?基本的な考え方

よくお客様から「相続と生前贈与のどちらを活用すべきか?」という質問をいただくことがよくありますが、この質問に対しての答えは、
「お客様一人ひとりの状況によってケースバイケース」
という元も子もないものなっています。
これは、単純な税率だけでなく、さまざまな条件や特例・控除を考慮した上で判断する必要があるからです。
ここからは、相続および生前贈与を行う上で少しでも多くのお金を手元に残すための、基本的な考え方を解説します。
基礎控除額以下の場合、相続対策は不要
原則、相続対象となる資産額が基礎控除額を下回る場合は、相続対策は不要です。
先述の通り、相続税は算出された基礎控除額を上回った金額の部分のみ課せられます。
相続資産が基礎控除額を下回るということは相続税が課税されないため、対策を取る必要がありません。
特例や控除を考慮する
相続資産が基礎控除額を上回り相続税が発生する場合は、各税金ごとの特例や控除を活用すれば多くのお金を大切な人に渡せます。
贈与税の控除など
贈与税は基礎控除以外にも以下の方法で控除が可能です。
| 最大控除額 | 内容 | |
| 相続時精算課税制度 | 2,500万円 | 贈与者の死後に相続税として清算 |
| 住宅取得資金 | 1,000万円 | 住居に掛かる資金を贈与 |
| 配偶者控除 | 2,000万円 | 婚姻期間20年以上のパートナーに贈与 |
| 教育資金 | 1,500万円 | 30歳未満の子および孫に教育資金として贈与 |
これらの控除制度を活用すれば、より多くの資産を大切な人に贈与できます。
相続税の控除など
相続税の場合、基礎控除に加え以下の方法を用いれば控除額が増え、税金の抑制につながります。
| 最大控除額 | 内容・相続対象者 | |
| 小規模住宅地 | 相続税評価額×80% | 330㎡までの土地を相続した場合に減額 |
| 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円または法定相続分のいずれか高い方 | 配偶者相続時に適用 |
| 未成年者の税額控除 | (20-年齢)×10万円 | 未成年相続時に適用 |
| 障害者の税額控除 | (85-年齢)×10万円 | 85歳未満の障害者が相続時に適用 |
| 相次相続控除 | (10-経過年数)×10 | 10年以内に相次相続が起きた場合 |
| 贈与税額控除 | 支払い済みの贈与税額 | 相続開始から3年以内に贈与を受けていた場合 |
| 寄付金控除 | 定めなし | 相続財産を国や自治体、特定の認定を受けた公益法人に寄付した場合に非課税 |
相続税の控除制度についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
【関連】相続税に関する控除の種類一覧まとめ!各制度を税理士が解説
遺産総額(課税価格)を抑制する
相続税を少しでも下げたいのであれば、生前贈与を活用して課税対象額を抑制しましょう。
生前贈与を活用すれば一定額までは非課税で他の人に資産を贈与できます。
実際に以下の条件の人が、生前贈与を活用した場合とそうでない場合を比較してみました。
【条件】
- 3億円の資産を所有している
- 法定相続人が妻と子2人
- 計2,000万円分を毎年生前贈与により非課税で贈与済(生前贈与加算なし)により非課税で贈与済(生前贈与加算なし)
<生前贈与を活用しなかった場合>
・基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
・課税遺産額=3億円-4,800万円=2億5,200万円
・相続税の総額 5,720万円
母:法定相続分に応ずる取得金額1億2,600万円×40%-1,700万円=3,340万円
子:法定相続分に応ずる取得金額6,300万円×30%-700万円=1,190万円
子:法定相続分に応ずる取得金額6,300万円×30%-700万円=1,190万円
上記を合計すると、5,720万円になります。
<生前贈与活用後>
・基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
・課税遺産額=(3億円-2,000万円)-4,800万円=2億3,200万円
・相続税の総額 5,020万円
母:法定相続分に応ずる取得金額1億1,600万円×40%-1,700万円=2,940万円
子:法定相続分に応ずる取得金額5,800万円×30%-700万円=1,040万円
子:法定相続分に応ずる取得金額5,800万円×30%-700万円=1,040万円
上記を合計すると、5,020万円になります。
2,000万円を生前贈与したケースでは、しなかったケースに比べて700万円も相続税を安く抑えられています。
相続税を低く抑える方法として、生前贈与の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
相続税と贈与税のどちらを選ぶべきか
 相続税と贈与税は、どちらを選択するかによって税負担が大きく変わる可能性があります。
相続税と贈与税は、どちらを選択するかによって税負担が大きく変わる可能性があります。
どちらを選ぶべきかは、個々の状況によって異なるでしょう。
こちらでは、より具体的なケースを想定し、相続税と贈与税の選択について詳しく解説します。
相続税を選ぶべきケース
相続税は、基礎控除額が大きく、税率も贈与税に比べて低い傾向にあります。
そのため、以下のケースでは相続税を選択する方が有利となる可能性が高いです。
相続財産が基礎控除額以下の場合
相続税は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分に課税されます。
したがって、相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されないため、相続財産の額によっては相続税を選ぶべきでしょう。
例えば、相続財産が3,000万円で、法定相続人が配偶者のみの場合、基礎控除額は3,600万円となるため、相続税は課されません。
相続財産の中に不動産が多い場合
被相続人が地主であった場合などは、相続財産の中に土地や建物などの不動産が多く含まれている場合も多いでしょう。
不動産は、相続税評価額が市場価格よりも低くなることが一般的です。
そのため、現金や有価証券に比べて相続税評価額が低くなり、相続税の負担を抑えることができます。
特に、小規模宅地等の特例を適用できる場合は、自宅の敷地などの評価額を大幅に減額できるため、相続税の負担を大きく軽減できます。
配偶者が相続する場合
相続税の計算が行われる際、配偶者は配偶者控除の特例(配偶者の税額軽減)を使えます。
配偶者控除を適用すると、配偶者が相続した財産の額が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までは相続税が課税されません。
ただし、相続人が法律上の配偶者であることはもちろん、たとえ非課税であっても相続税の申告をしなければならない点に注意が必要です。
相続財産が将来的に値上がりする可能性が高い場合
不動産や株式など、今後価値が上がる可能性が見込める財産を相続する場合、「相続時精算課税制度」を利用するとよいでしょう。
相続税は、相続開始時の財産の評価額に基づいて課税されます。
そのため、将来的に値上がりする可能性が高い財産は、相続時に評価額が確定するため、贈与税よりも税負担が少なくなる可能性があります。
相続時精算課税制度とは、贈与税の計算方法における特例の一つで、原則として60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与について、2,500万円までの贈与税を非課税とする制度です。
贈与者が亡くなった際には、相続税の計算時に贈与財産を相続財産に加算して相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除して相続税を納付します。
そのため、相続時に課税されるのは贈与したときの2500万円分のみで、仮に相続財産の価値が上がったとしても上がった分に関しては課税されないため、大きな節税効果を生み出せます。
贈与税を選ぶべきケース
贈与税は、相続税に比べて税率が高い傾向にありますが、生前贈与を計画的に行うことで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
以下のケースでは贈与税を選んだ方が税負担を軽減できるでしょう。
相続財産が基礎控除額を大幅に超える場合
相続税は、相続財産が多いほど税率が高くなります。
そのため、相続財産が基礎控除額を大幅に超える場合は、生前贈与によって相続財産を減らすことで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
また、暦年贈与を活用し、毎年110万円までの贈与を複数年行うことで、贈与税をかけずに相続財産を減らすことができます。
特定の相続人に特定の財産を渡したい場合
相続では、遺産分割によって財産が分配されますが、遺産分割協議がまとまらない場合や、特定の相続人に特定の財産を渡したい場合は、生前贈与が有効です。
例えば、特定の子供に事業を承継させたい場合や、特定の子供に不動産を渡したい場合をはじめ内縁のパートナーに財産を譲りたい場合などにも有効でしょう。
相続税の納税資金を準備したい場合
相続税は、相続開始から10ヶ月以内に現金で一括納付する必要があります。
しかし、相続財産の中に不動産や有価証券が多く、納税資金が不足する可能性がある方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、生前贈与によって納税資金を準備することができます。
例えば、子供に毎年贈与を行い、贈与された子供がその資金を貯蓄すれば、相続税の納税資金を準備することができます。
相続財産の金額や相続人の立場によって相続税を選ぶべきか、贈与税を選ぶべきか異なります。
どちらを選んでもさまざまな特例や控除を利用できるため、しくみを知って該当するものを利用するのが得策でしょう。
大阪・東京で相続対策・生前贈与にお困りの方はハートランド税理士法人へ

相続対策のひとつとして、生前贈与は非常に有効な手段といえます。
しかし、贈与税や相続税の計算は非常に複雑であり、一般の方が生前贈与と相続どちらがお得かを判断するのは困難です。
そのため、相続や贈与に関するお困りごとは、専門家である税理士に任せるのが得策です。
ハートランド税理士法人では、相続および生前贈与に関する相談を承っております。
「生前贈与と相続、自分のケースではどちらがお得なのかわからない」という方は、お電話やメール、公式LINEからいつでもお気軽にご相談ください。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。