<この記事は約 26 分で読めます>
「うちも相続税の申告をしたけど、本当にこれで大丈夫なんだろうか…」そんな不安を感じていませんか?
実は、相続税を申告した方の約10件に1件は税務調査の対象になっており、その多くで申告漏れが指摘されています。
特に、申告書の内容に不自然な点がある場合や、財産の把握が不十分な場合は、調査対象となるリスクが高まります。
本記事では、以下の8つについて解説します。
- 相続税の税務調査とは
- 税務調査の種類
- 相続税の税務調査が入る時期
- 相続税の税務調査の流れ
- 税務調査に入られる可能性が上がってしまうポイント
- 税務調査に入られないために気を付けるべきこと
- 相続税の税務調査で指摘されやすいポイント
- 相続税の税務調査で受ける可能性のある質問
税務署が注目するポイントや、信頼できる税理士の選び方も紹介しますので、「できれば調査を避けたい」「きちんと申告して安心したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続税の税務調査とは

相続税の税務調査とは、提出された相続税申告書の内容が正確かどうかを、税務署が確認するために行う調査です。国税庁によれば、特に申告漏れが疑われるケースでは、一定の割合で実地調査が実施されています。
| 税務調査の目的 | ・財産の申告漏れや過少申告を防ぐこと ・故意の財産隠しや名義財産を明らかにすること ・適正な課税を確保すること |
| 税務調査で重点的に確認されるポイント | ・現金や預貯金(特に名義預金)の有無 ・不動産の評価方法(路線価・倍率方式の適用ミスなど) ・自社株など非上場株式の評価の妥当性 ・贈与財産との区別があいまいな財産の存在 |
税務調査の実施はすべての申告に対して行われるわけではなく、国税庁の「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の課税対象者のうち約10%程度が調査対象になっています。
なお、税務署は、以下のような要素をもとに調査対象を選定しています。
- 提出された相続税申告書の記載内容
- 財産の種類や評価額
- 相続人の人数や関係性
- 被相続人や相続人の過去の納税状況
申告内容に不自然な点や不備があると、調査対象となるリスクが高まります。調査を受けると、過少申告加算税や重加算税などの追徴課税が課される可能性があるため、初めから正確な申告を行うことが何よりも重要です。
ここからは、実際にどのような種類の税務調査があるのか、調査の流れ、質問内容などについて詳しく解説していきます。
税務調査の種類

相続税の税務調査には、大きく分けて以下の2種類があります。
- 任意調査
- 強制調査
それぞれの調査には異なる目的と手続きがあり、対応方法も変わってきます。
以下で、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
強制捜査
強制捜査とは、裁判所の令状に基づき、納税者の同意なしに行われる調査です。
通常の税務調査(任意調査)とは異なり、脱税や重大な申告漏れの疑いが強い場合に実施されます。
例えば、資産隠しや虚偽申告などが明らかな場合、税務署は国税局査察部(マルサ)と連携し、帳簿やパソコン、預金通帳などの押収を行います。
捜査は早朝に始まり、関係先も含めて一斉に行われることが一般的です。脱税額が大きく悪質と判断された場合は、刑事告発され、罰金や懲役刑を受けることもあります。
相続税においては稀なケースですが、過去には多額の名義預金が発覚し、強制捜査に発展した事例もあります。
任意捜査
任意捜査は、税務署が納税者に対して事前に連絡し、同意を得た上で行う調査で、相続税の税務調査のほとんどがこの形です。
強制的に資料を押収することはできませんが、調査官は申告内容に疑義がある点を丁寧に確認していきます。
通常は調査の1か月前までに電話などで日程調整が行われ、当日は自宅または税理士事務所で実施されます。
調査では、被相続人の預貯金や不動産、過去の贈与、名義預金の有無などが中心に確認されます。
質問内容には家族構成や財産管理の実態なども含まれ、場合によっては複数日にわたることもあります。
誠実な対応と事前準備が調査の負担を軽減し、誤解を防ぐ鍵となります。
相続税の税務調査が入る時期

相続税の税務調査が行われるタイミングや流れについて、以下のようなポイントを押さえておくことが大切です。
- 調査の時期
相続税の税務調査は、申告書を提出してから通常1年〜1年半以内に行われるのが一般的です。
- 調査対象の選定
税務署は提出された申告書の内容を精査し、不審点や不明確な点があると判断した場合、調査対象として選定します。
- 申告期限について
相続税には明確な申告期限があり、被相続人の死亡から10か月以内に申告および納税を行う必要があります。
- 調査通知のタイミング
申告後、税務署は一定の審査期間を経て、問題があると判断されれば調査の通知が届きます。
- 通常よりも早い段階の調査
明らかな申告漏れや過去の贈与の記録が確認されている場合、通常より早い段階で調査が行われるケースもあります。
- 調査が行われないケース
逆に、財産内容が明瞭であり、相続税の専門家によって正確な申告がなされている場合は、調査が実施されないことも少なくありません。
これらのポイントを理解し、適切な申告と対策を講じておくことで、余計な不安やトラブルを避けることが可能です。
相続税の税務調査の流れ

相続税の税務調査は、大きく3つのステップに分かれて進行します。
それぞれの段階で適切な対応を行うことが、余計なトラブルを防ぐために重要です。
- 調査の連絡
- 調査当日の対応
- 調査結果の通知
このように、相続税の税務調査には明確な流れがあります。
各段階で冷静に準備・対応することが、安心につながります。
税務調査の連絡を受ける
相続税の税務調査は、通常申告後1年から3年以内に税務署から連絡が来ます。
連絡は電話や書面で通知され、調査の日時や場所、担当者の名前が明記されています。
税務調査は原則任意調査ですが、適切な対応を怠ると不利になることもあります。
通知を受けたら、まずは冷静に内容を確認し、調査に必要な書類や資料を漏れなく準備しましょう。
財産目録や銀行通帳、保険契約書などを整理し、誤りのない申告内容を再確認することが重要です。
また、調査に不安がある場合は、相続税に詳しい税理士に相談し、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。
これにより、スムーズな調査対応が可能となり、余計なトラブルを避けられます。
税務調査に対応する
税務調査当日は税務署の担当者が申告内容や提出資料をもとに調査を行います。
調査は自宅や税理士事務所、場合によっては税務署で行われることがあります。
調査員からは財産の詳細や取得経緯、評価方法などについて質問があり、丁寧に答えることが求められます。
質問に不明点や疑問があれば、正直に伝えつつ、必要に応じて税理士に相談しながら対応しましょう。
調査は数時間から数日に及ぶこともあるため、事前に十分な準備をして臨むことが重要です。
また、調査中に新たな資料が必要になることもあるため、柔軟に対応できる体制を整えておくと安心です。
誠実な対応を心がけることで、税務署との信頼関係を築き、調査が円滑に進みます。
調査結果を確認する
税務調査の連絡は、通常、税務署から書面や電話で事前に通知されます。
通知には調査の目的や日程、調査に必要な書類の案内が含まれています。
通知を受け取ったら、まず内容をよく確認し、準備を始めることが大切です。
税務調査は相続税申告の正確性を確認するために行われ、調査官が被相続人の財産内容や申告書の内容について詳しく質問します。
調査にあたっては、必要書類の整理や関係者との連携、専門の税理士への相談が不可欠です。
しっかりと準備して臨むことで、調査がスムーズに進み、不必要なトラブルや追加納税のリスクを減らすことができます。
また、税務署の指摘事項を正しく理解し、適切な対応を取ることが重要です。
これにより、税務調査後の修正申告や異議申し立てなども円滑に行えます。
早めの準備と専門家の協力が税務調査成功の鍵となります。
税務調査に入られる可能性が上がってしまうポイント
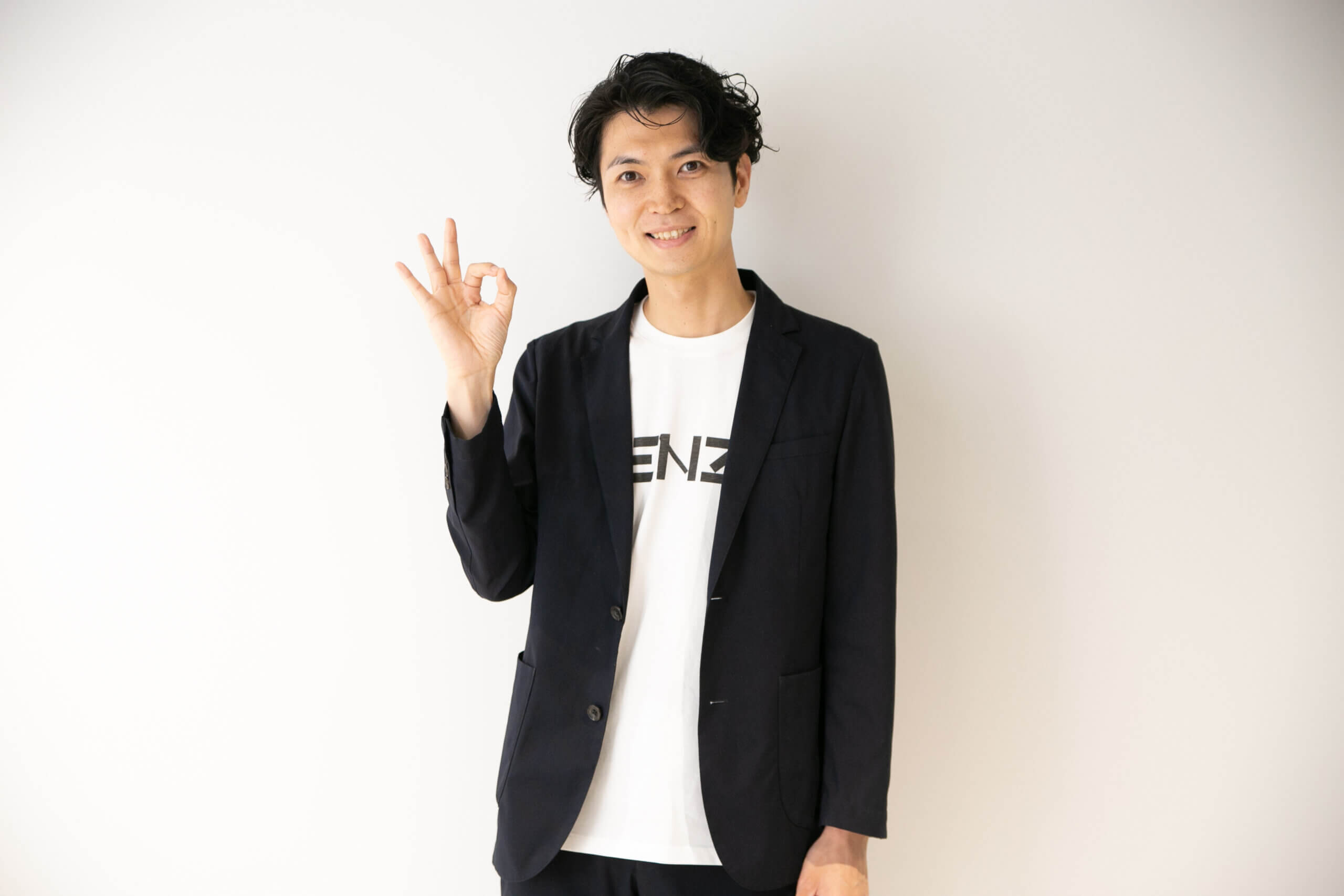
相続税の申告において不備や漏れがあると、税務署から調査対象として選ばれるリスクが高まります。
特に以下のようなケースは、調査を受けやすくなるため注意が必要です。
- 申告書の内容に不備や漏れがある場合
- 相続財産に対して不自然な借り入れがある場合
- 相続税に不慣れな税理士へ依頼している場合
- 生前の所得や資産売却との申告にズレがある場合
これらの点に心当たりがある場合は、事前に専門家のチェックを受けるなどして、申告内容の見直しを行うことが大切です。
適切な対策を講じることで、不要な調査や追徴課税のリスクを回避できます。
申告書に不備や申告漏れがある
相続税の申告書に不備や記載漏れがあると、税務調査に入られる可能性が非常に高くなります。
国税庁の「相続税の調査の手引き」では、特に財産評価の誤りや未申告資産の存在が調査対象の重要ポイントとされています。
例えば、土地の評価額が実際よりも低く申告されていたり、預貯金や株式などの金融資産が申告から漏れている場合、過少申告加算税や重加算税の対象となり得ます。
また、相続税申告書の計算ミスや添付書類の不足も税務署から疑義を招き、調査のきっかけになります。
これらは納税者の過失であっても税務調査を受ける原因となるため、申告書作成時には細心の注意が必要です。
国税庁は適正かつ正確な申告を強く推奨しており、申告内容の透明性が税務調査を避ける上で重要としています。
相続財産に見合わない額を借り入れている
相続税の申告において、相続財産の額に見合わない借入金がある場合も税務調査の対象になりやすいです。
国税庁の資料によると、例えば相続開始前に大きな借入れをしているにもかかわらず、その資金の使途や返済状況が不透明な場合、税務署は借入金の真実性を疑い調査を行います。
特に借入金が財産隠しの手段として使われている可能性があると判断されると、税務署は詳細な資金の流れや契約内容の確認を実施し、不正が認められれば重加算税の対象になることもあります。
借入金は債務控除の対象となるため、正確な申告が必要ですが、借入れの証拠書類が不十分だったり、相続財産との整合性が取れていない場合、税務調査に繋がるリスクが高まります。
借入れに関する書類はきちんと保存し、税理士と相談しながら申告書を作成することが大切です。
相続が専門でない税理士に相続税の申告を依頼している
相続税の申告は専門知識が求められるため、相続に精通していない税理士に依頼すると申告内容に誤りが生じやすくなります。
国税庁の資料や税務専門誌によると、相続税申告のミスは、申告漏れや評価額の過小計上などが多く、これらが発覚すると税務調査の対象となりやすいです。
専門知識のない税理士は最新の税制改正や複雑な評価方法について理解が不足しがちであり、結果として適正な申告が難しくなります。
特に不動産評価や贈与税との関係、財産の把握が不十分だと税務署の目に留まりやすいです。
専門税理士に依頼することで、正確かつ漏れのない申告が期待できるため、税務調査のリスクを下げることができます。
税理士選びは、相続税申告の成功において重要なポイントとなるため、実績や専門性をしっかり確認することが推奨されています。
生前の不動産所得や株式売却代金に対して相続税の申告額が少ない
生前に被相続人が得ていた不動産所得や株式の売却代金に関して、相続税の申告が適切に行われていないケースも税務調査でよく指摘されるポイントです。
国税庁の「相続税の調査事例集」(2023年)によると、生前の所得に対する課税が不十分であったり、売却代金の一部が申告から漏れていたりする場合、税務署は申告内容の正確性を疑い調査を強化します。
特に、不動産の賃貸収入や株式譲渡に関する所得は把握が難しいため、申告漏れや過小申告のリスクが高いです。
税務調査ではこれらの点を重点的にチェックし、財産評価の整合性や所得の申告状況が調べられます。
したがって、生前の財産に関わる収入や資産の移動については漏れなく申告し、専門家の助言を受けることが重要です。
このように適切に対応することで、税務調査の対象となるリスクを軽減することが可能です。
税務調査に入られないために気を付けるべきこと

相続税の税務調査は、申告内容に不備や疑わしい点がある場合に実施されますが、以下のような対策を講じることで調査されるリスクを下げることが可能です。
- 財産を正確に評価し、適正な申告を行う
- 財産の全容をしっかりと把握する
- 相続税に強い税理士に相談・依頼する
- 生前対策をしておく
これらの対策は、実際に国税庁が公表する税務調査の事例においても有効とされています。
相続税の申告は一生に何度もあるものではありません。だからこそ、事前準備を万全に整え、安心して申告を終えることが大切です。
適正申告をする
相続税における適正申告は、税務調査を回避するための最も基本かつ重要な要素です。
適正申告とは、財産の全体像を正確に把握し、相続税法に則って正確に評価・申告することを意味します。
たとえば、不動産の評価を実勢価格ではなく、路線価などの法定の方法で行うことや、非上場株式や名義預金の取扱いを正確に行うことなどが含まれます。
申告漏れや過少申告があると、後日税務署から調査の連絡を受ける可能性が高まります。
特に国税庁は、金融機関や不動産登記情報など多くの外部情報を参照して申告内容をチェックしており、少しの不備でも疑義を持たれることがあります。
誤りのあった申告が税務調査で判明した場合、追徴課税の対象となるだけでなく、加算税や延滞税が発生する可能性もあります。
そのため、正確な資料収集と知識に基づいた慎重な申告が不可欠です。
相続財産調査を漏れなく行う
相続税申告において、財産の全容を正確に把握することは非常に重要です。
漏れのある財産調査は申告漏れにつながり、税務調査の対象となる大きな要因となります。
財産調査では、被相続人名義の預貯金や不動産、有価証券のほか、家族名義の口座の中に実質的に被相続人の財産が含まれているケース(名義預金)も注意が必要です。
さらに、生命保険の受取金や貸金庫の中身、未登記不動産、非上場株式、タンス預金、仮想通貨なども対象になります。
また、負債や葬儀費用などの控除対象となる債務も正確に調査しておく必要があります。財産の内容が複雑な場合には、複数年にわたる通帳記録の精査や不動産の登記簿・固定資産税評価証明書の収集など、詳細な裏付けを持つことが不可欠です。
このような入念な財産調査が適正な申告につながり、税務調査を未然に防ぐ一助となります。
相続を専門とする税理士に依頼する
相続税の申告は通常の所得税や法人税とは異なる高度な専門知識を要する分野です。
そのため、相続税に不慣れな税理士では、見落としや評価ミスが発生しやすく、結果的に税務調査につながるリスクが高まります。
相続税の経験が豊富な税理士は、非上場株式や借地権、地積規模の大きな宅地の評価といった複雑な財産に対する適切な対応が可能であり、税務署から指摘されにくい堅実な申告を行うことができます。
実際、国税庁が公表する資料でも、税理士を通した申告のうち専門家によるチェックが甘い場合には、申告漏れが見つかる割合が高いとされています。
また、専門税理士は事前の生前対策や節税提案、将来の税務調査への対応アドバイスも行えるため、依頼者にとって多くのメリットがあります。
相続税申告においては、税理士選びがその後のリスクを大きく左右する重要な判断といえるでしょう。
財産目録を作成して遺言書を残す
相続が発生した際に財産の全体像を正確に把握できるかどうかは、申告ミスや争いを防ぐ上で非常に重要です。
そのためには、生前のうちから財産目録を作成し、遺言書を残しておくことが有効です。
財産目録とは、被相続人の財産の種類・内容・評価額などを明記した一覧表であり、預貯金や不動産、有価証券、負債などを正確に記載します。
これがあることで、相続人が財産の所在や内訳を把握しやすくなり、申告漏れを防げます。
また、遺言書には遺産分割の意思が記載されているため、相続人間のトラブル回避にも役立ちます。
特に公正証書遺言であれば、法的効力が高く、遺言執行もスムーズに行えます。
さらに、財産の所在が明確になることで、税務署に対しても申告内容に信頼性があると判断され、調査のリスクが下がることもあります。
円滑な相続と適正な申告のために、事前の準備としてこれらの書類を整えておくことが望まれます。
相続税の税務調査で指摘されやすいポイント

相続税の税務調査では、以下の3つの分野が「申告漏れが発覚しやすい重点エリア」として、特に厳しくチェックされます。
- 被相続人の預貯金
死亡直前に多額の現金が引き出されていた場合、税務調査ではその使途や引き出し人について厳しく追及されます。
明確な使途説明ができない場合、「使途不明金」として相続財産に組み入れられるリスクがあります。
- 生命保険金
契約者や保険料負担者が被相続人で、受取人が別人になっている場合、相続税の非課税枠を超えた金額に課税されることがあります。
特に「契約形態のずれ」は典型的な申告ミスとして見逃されません。
- 名義預金
家族名義の預金であっても、実際には被相続人が通帳や印鑑を管理し、資金を出し入れしていた場合、「実質的には被相続人の財産」とみなされます。
これが否認された場合、過少申告加算税や重加算税の対象となることもあるため、十分な注意が必要です。
国税庁の統計や実務上のデータによれば、相続税の税務調査の約8割で申告漏れが発覚しており、その大半が上記の3項目に集中しています。
これらは調査官が比較的容易に資料照合できるうえ、金額も大きくなりやすいため、調査対象として優先的に確認されます。
そのため、事前に証拠書類を揃え、適切な説明ができる体制を整えておくことが調査回避の鍵となります。
被相続人の預貯金について
被相続人の預貯金は、相続税の税務調査において最も重点的に確認される資産項目です。
国税庁の統計でも、申告漏れが最も多く見つかるのが現金・預貯金であると明記されています。
特に注意すべきは、被相続人が生前に引き出した大口の現金や、死亡直前に不自然な出金がある場合です。
たとえば「介護費用」として数百万円単位の現金が引き出されているが、使途が不明確であると、「隠し財産ではないか」として相続財産に加算されることがあります。
また、銀行口座の名義が被相続人であっても、実質的な管理や使用が他人であれば贈与と見なされるケースもあるため、名義と実態の整合性が重要です。
金融機関から入手できる「取引履歴」や、現金の使途を証明する領収書・契約書などを事前に整理しておくことで、調査時のリスク軽減につながります。
被相続人の生命保険について
生命保険もまた、相続税の税務調査で申告漏れが多く指摘される項目です。
生命保険金は原則として「みなし相続財産」として課税対象となりますが、非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)を超える部分については相続税が課せられます。
実務上よくある問題は、「契約者」と「保険料負担者」が被相続人であるにもかかわらず、保険金の受取人が相続人になっているケースです。
この場合、非課税枠を超えた金額が正確に申告されていないと、調査で追加課税の対象になります。
また、保険契約書を遺族が把握していなかった場合、保険金の存在自体を見落とすリスクもあります。
税務署は保険会社からの支払調書を基に照会できるため、保険金の存在を隠すことはほぼ不可能です。
相続発生時にはすべての保険契約の内容・受取人・保険料負担者を確認し、適切な申告を行う必要があります。
家族名義の預金について
家族名義の預金、いわゆる「名義預金」は、実質的な所有者が被相続人であると税務署に判断されやすい典型的な申告漏れ対象です。
たとえば、被相続人が孫名義の口座に毎年数十万円を振り込んでいた場合でも、その資金の出どころが被相続人であり、口座の通帳や印鑑が被相続人の管理下にあれば、実質的には被相続人の財産とみなされます。
このような場合、形式的に名義が他人であっても、実態に即して課税されます。
相続税申告では、このような名義預金の実態調査が重要であり、過去の贈与契約書の有無や通帳の保管状況、口座開設の経緯などが問われます。
調査では「誰が口座を開設し」「誰が管理していたか」「使われた実績があるか」が重視されるため、名義と実態が一致している証拠を残しておくことが重要です。
名義預金に関する誤解が原因で重加算税の対象になることも多いため、十分な注意が必要です。
相続税の税務調査で受ける可能性のある質問

相続税の税務調査では、財産の申告内容が適正かどうかを確認するために、相続人に対して非常に具体的な質問がされます。
調査官は、単なる金額の確認ではなく、被相続人の生前の生活状況や財産管理の実態についても踏み込んで質問する傾向にあります。
以下は、実際に聞かれる可能性のある代表的な質問です
- 被相続人の通帳や印鑑は誰が管理していましたか?
- 死亡直前の現金の引き出しは何の目的でしたか?
- 家族名義の預金口座を、被相続人が管理していたことはありますか?
- 被相続人の生活費や介護費用は誰が負担していましたか?
- 被相続人が現金をどこに保管していたか把握していますか?
- 生前に贈与を受けたことはありますか?それは記録として残っていますか?
- 生命保険金の受け取りは誰が手続きし、使用目的は何でしたか?
- 遺産分割協議はどのように進めましたか?その経緯は文書に残っていますか?
これらの質問に対し、曖昧な返答や記録の不備があると、調査官に「申告漏れ」や「隠ぺいの可能性あり」と判断される恐れがあります。
事前に相続人同士で事実を共有し、必要に応じて税理士と連携して答えを整理しておくことが、スムーズな対応につながります。
特に名義預金や現金の保管場所、贈与の有無といった点は重点的に確認されるため、準備は慎重に行いましょう。
大阪・東京で相続税の計算・申告にお悩みの方はハートランド税理士法人へご相談ください
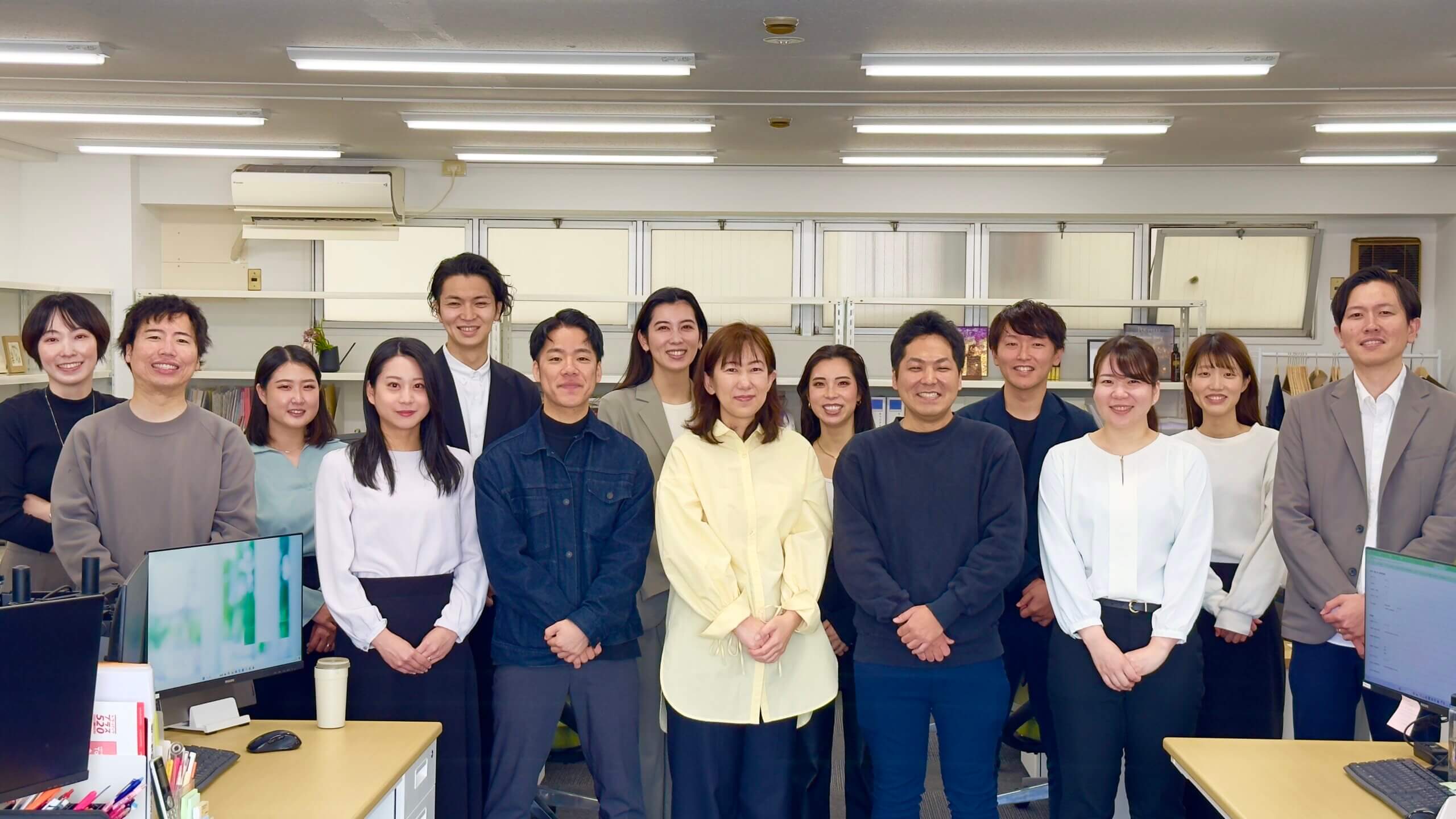
相続税の申告を終えた後も、「税務調査が来るかもしれない」と不安を感じる方は少なくありません。
実際には、申告から1年から2年程度の間に、調査の連絡が来ることが多く、特に申告内容に不自然な点や説明が不足している部分があると、調査対象となるリスクが高まります。
相続税の税務調査では、財産の名義、預金の出入り、不動産の評価などが重点的に確認されるため、書類の整備や根拠の明確化が極めて重要になります。
調査を避けるためには、最初の申告段階でミスのない書類を作成し、税務署の視点を意識した対応をすることが求められます。
ハートランド税理士法人では、税務調査を見据えた申告サポートを行い、安心して相続手続きを進めていただけるよう努めています。
少しでも不安を感じた方は、お電話やメール、LINEからご相談ください。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。













