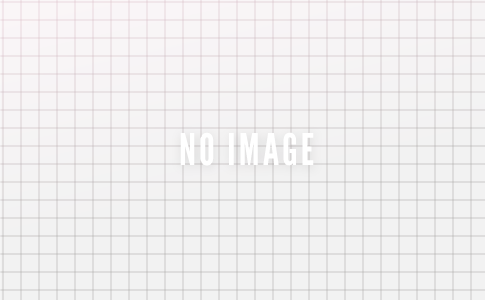<この記事は約 15 分で読めます>
相続税の申告、どの税理士に依頼すればいいのか迷っていませんか?
「料金の違いは?」「本当に専門の人なの?」と、不安や疑問を抱える方は少なくありません。
相続は人生で何度も経験するものではないからこそ、信頼できる専門家選びが重要です。
本記事では、以下の5つについて解説します。
- 相続税理士を選ぶ6つのポイント
- 税理士の委託が必要な2つのシーン
- 相続に強い税理士の3つ探し方
- 相続税専門の税理士に依頼するメリット3選
- 相続税理士に依頼する際の注意点2選
この記事を読めば、相続に強い税理士を選ぶために必要な情報がすべてわかります。
相続税理士を選ぶ6つのポイント

相続税理士を選ぶ際には、以下の6つの観点を意識することが重要です。
- 相続税に特化した豊富な実績があるか
- 税理士報酬が適正かどうか
- 専門性を裏付ける書籍やメディア実績があるか
- 他士業との連携体制が整っているか
- 相続税の申告や還付の対応実績があるか
- 対応が迅速かつ的確かどうか
これらの要素を総合的に判断することで、自身の状況に適した相続税理士を見つけやすくなります。
相続は一生に何度も経験するものではなく、適切な専門家を選べるかどうかで納税額や対応のスムーズさが大きく変わります。
以下に、各ポイントを詳しく解説していきます。
相続税専門で実績の豊富な税理士かどうか
相続税の申告業務は、他の税目と比べて専門性が高く、知識だけでなく実務経験が問われます。
特に、不動産の評価や非上場株式の取り扱い、二次相続の影響など、相続税特有の複雑な問題に対応するには、経験豊富な税理士でなければ正確な判断が難しくなります。
さらに、税務調査が発生した際にも、相続税の実務に慣れた税理士であれば、過去の事例に基づいた適切な対応が可能です。
専門性の有無は、ホームページの実績掲載や相談時の対応内容から判断できます。
相続税の申告件数が多く、定期的に相続関連のセミナー講師を務めている税理士などは、信頼性の高い候補です。
面談時には、これまでの取り扱い件数や依頼者の属性(例:資産規模や財産構成)について確認し、自身のケースに合った対応ができるかを見極めましょう。
税理士報酬が適正かどうか
税理士に支払う報酬が妥当であるかどうかは、依頼前に必ず確認すべき重要なポイントです。
報酬の相場は地域や財産の内容によって異なりますが、全国平均では30万〜60万円前後が一般的とされています。
ただし、報酬が極端に高い場合や安すぎる場合は注意が必要です。
高額な費用がかかる場合は、なぜその金額になるのか、どこまでが報酬に含まれているのかを丁寧に確認しましょう。
一方、極端に安価な報酬を提示してくる税理士には、業務の質や経験値に不安があることもあります。
複数の税理士に見積もりを依頼し、相場と比較しながら適正な金額で依頼できるかを判断しましょう。
相続税に関する書籍の出版やメディア掲載があるかどうか
税理士が相続税関連の書籍を執筆していたり、新聞やテレビなどで取り上げられている場合、その専門性や実績が一定の評価を受けていると判断できます。
出版歴やメディア出演は、その税理士が多くの相続案件に携わっており、一般向けにも分かりやすく情報発信を行っている証拠です。
信頼性の高い情報源として、その実績が依頼先選びの参考になります。
ただし、見かけの実績だけでなく、内容が相続税申告に直結しているかも確認しましょう。
メディア掲載歴や書籍情報は、事務所のホームページに記載されていることが多いので、チェックしておくと安心です。
弁護士など他の専門家と連携しているかどうか
相続には税金以外にも、遺産分割や登記、紛争などさまざまな法律問題が関わるため、税理士が他士業と連携しているかどうかも大切な判断材料です。
たとえば、弁護士と連携していれば、相続人間のトラブルにも速やかに対応できます。
司法書士と組んでいれば、登記変更なども合わせて進められるため、依頼者の負担が大きく軽減されます。
税理士が他士業との連携ネットワークを持っている場合は、事務所の紹介ページなどに記載されていることが多いため、確認しておきましょう。
相続税の「申告や還付の実績」が豊富かどうか
申告や還付の実績が豊富な税理士は、制度の細かな点まで熟知しており、依頼者の状況に応じて最適な申告方法を提案できます。
特に、払いすぎた税金を取り戻す「相続税の還付」は専門知識がなければ対応が難しい分野であり、これに対応できる税理士は非常に限られています。
実績のある税理士は、財産評価の見直しや適用漏れの控除を見つける力があり、結果として納税額の適正化や還付につながるケースもあります。
相談時には、過去にどのような申告・還付事例を経験しているか具体的に尋ねると良いでしょう。
対応は的確でスピーディーかどうか
相続税申告には期限(原則として相続開始から10か月以内)があるため、税理士の対応のスピードは非常に重要です。
連絡への返答が遅い、説明が曖昧、必要書類の案内が遅れるといった対応では、依頼者側に大きな不安と負担がかかります。
スムーズな対応ができる税理士は、初回相談の時点から分かりやすく丁寧な説明を行い、必要なスケジュール管理も徹底しています。
相談の段階で、返信の早さや説明の明確さなどを観察し、信頼できる対応かを見極めましょう。
税理士の委託が必要な2つのシーン

相続税理士のサポートが特に有効な場面があります。
次の2つのようなケースでは、自己判断による申告は困難であり、専門家に依頼することでリスク回避と申告の正確性が確保されます。
相続人がたくさんいる場合
相続人が複数人いる場合、相続財産の分割や申告方針について意見が分かれることがよくあります。
誰がどの財産を取得するか、どのように税額を分担するかなど、調整が必要な場面でトラブルが発生することも珍しくありません。
税理士が関与することで、中立的な立場から適正な分割案を提案し、申告作業を効率よく進めることが可能になります。
相続人が3人以上いる場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
相続財産に分割が難しい不動産や宝石が含まれる場合
不動産や高額な宝石、美術品などは現物のままでは平等に分けることが難しく、評価方法や分割の仕方によって相続人間の対立を生みやすい資産です。
こうした財産が相続に含まれる場合は、専門的な評価と、税法に基づいた適正な分割案の提示が求められます。
税理士は、不動産鑑定士などと連携しながら財産評価を進め、税額への影響を踏まえた形で分割の助言を行うことができます。
専門家の関与により、無用なトラブルを未然に防げます。
相続に強い税理士の3つ探し方

自分に合った相続税理士を見つけるには、以下の3つの方法が有効です。
- 税理士事務所のホームページで専門性や実績を確認する
- 実際に面談を行い、相性や説明力を比較する
- 信頼できる知人から紹介を受ける
以下で、それぞれの探し方のポイントを解説します。
税理士ホームページを活用する
多くの税理士事務所は自社ホームページを通じて業務内容や実績を公開しています。
特に相続税に力を入れている事務所では、申告件数、対応地域、料金体系、事例紹介などが明記されており、依頼前に比較検討する材料として有用です。
また、スタッフ紹介や代表のあいさつなどを読むことで、事務所の雰囲気や方針も把握できます。
検索時には「地域名+相続税理士」といったキーワードを活用し、複数の事務所を比較してみましょう。
複数の税理士と面談する
税理士の選定は「相性」が重要な要素になります。
同じ業務内容であっても、説明のわかりやすさや対応の柔軟性は税理士ごとに異なります。
面談を通じて、自分の状況に対してどのように対応してくれるのかを確認し、最も信頼できる相手を選びましょう。
最低でも2〜3人と面談することで、比較対象が明確になり、より納得感のある選択が可能になります。
友人や家族の紹介を受ける
すでに相続税申告を経験した友人や親族から税理士を紹介してもらう方法も信頼性が高い探し方です。
実際に依頼した経験に基づいた評価を聞けるため、情報の正確性と信頼度が高くなります。
紹介を受けた税理士でも、自分自身のケースと合っているかどうかを確認するために、一度は直接相談するようにしましょう。
相続税専門の税理士に依頼するメリット3選

相続税の申告を専門税理士に依頼することで、以下のような3つの大きなメリットがあります。
- 手続きの負担を大幅に軽減できる
- 節税の可能性が高まる
- 税務調査のリスクを回避できる可能性がある
これらの利点は、時間や精神的な負担を軽減するだけでなく、最終的な納税額の抑制にもつながります。
相続税申告に不慣れな方にとっては、専門家のサポートがあることで安心感と正確性が確保されます。
手間や時間がかからず申告作業ができる
相続税の申告には、多くの書類収集・財産評価・税法の確認など、煩雑な作業が伴います。
個人で対応しようとすると、膨大な時間と労力がかかるだけでなく、申告内容にミスが発生するリスクも高くなります。
一方で、相続税に強い税理士に依頼すれば、必要書類の確認から申告書の作成まで一括して対応してもらえるため、申告期限までに余裕を持って手続きを進めることが可能です。
時間的制約のある相続人にとっては、専門家への依頼は非常に有効な手段です。
相続税を節税できる
相続税にはさまざまな特例や控除制度が存在しており、これらを適切に活用できるかどうかで納税額が大きく変わります。
たとえば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、養子の利用など、節税の余地があるポイントを見落とさずに活用できるかどうかは、税理士の知識と経験に大きく依存します。
相続税専門の税理士は、これらの制度を適切に判断し、最も節税効果の高い申告方法を提案してくれるため、最終的な納税額を抑えることが可能になります。
余計な税務調査を回避できる
相続税申告は、内容に不備や疑義があると、税務署から調査対象として選ばれる可能性があります。
税務調査には時間と精神的な負担が伴うため、可能な限り避けたいものです。
相続税専門の税理士に依頼することで、記載内容の正確性が担保され、税務署に対しても信頼性の高い書類を提出できます。
また、万が一税務調査が行われた場合でも、税理士が代理人として対応するため、依頼者自身の負担を軽減することができます。
相続税理士に依頼する際の注意点2選

相続税理士に依頼する際は、メリットだけでなく以下の2つの注意点にも目を向けておくことが大切です。
- 成果報酬型の料金体系には慎重に対応する
- 相場よりも安すぎる報酬提示には警戒が必要
これらを理解した上で依頼することで、トラブルを未然に防ぎ、納得のいくサービスを受けることができます。
成果型の料金体系に注意が必要
一部の税理士事務所では、「節税できた金額の○%を成功報酬として支払う」といった成果報酬型の料金体系を採用している場合があります。
一見、依頼者にとって合理的に見えるこの方式ですが、適用される控除や特例は法的に認められたものであり、それ自体が成果とは言いにくい側面もあります。
また、報酬金額が不明確になる可能性もあるため、見積もりの段階で総額を把握しておくことが重要です。
契約前には、報酬体系と内訳をしっかり確認し、納得のうえで進めるようにしましょう。
極端に安価な報酬設定には注意
税理士報酬が相場よりも極端に安い場合、業務品質が十分でない可能性があります。
申告漏れや誤った評価によって、後に追加納税や税務調査が発生するリスクも否定できません。
特に相続税は1件あたりの負担額が大きいため、初期費用だけで判断せず、内容と対応範囲、実績などを総合的に評価することが求められます。
適正な価格で適切な業務を提供している税理士を選ぶことが、長期的な安心につながります。
大阪・東京で相続税の計算・申告にお悩みの方はハートランド税理士法人へご相談ください

相続税の申告を税理士に依頼する場合、その選び方によって結果は大きく変わることがあります。
経験や実績のある税理士であれば、複雑な財産の評価や特例の適用においても、的確な対応が可能です。
一方で、相続税をあまり扱っていない税理士に依頼した場合、思わぬ税負担が発生するなどのリスクもあります。
また、依頼後のコミュニケーションや対応の丁寧さも非常に重要です。
相続は感情的にも大きな負担となる場面が多いため、安心して任せられる相手であることが大切です。
信頼できる税理士と出会えれば、税務面だけでなく相続全体がスムーズに進みます。
ハートランド税理士法人では、相続に特化したスタッフが在籍し、丁寧でわかりやすい説明と確かな対応で多くのお客様から信頼をいただいております。
税理士選びで迷われている方も、まずはお気軽にご相談ください。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。