<この記事は約 13 分で読めます>
個人事業主として活動されている方が法人化するとどのようなメリット・デメリットがあるのか気になる点かと思います。
個人事業主が会社設立をすると、主に以下のようなメリットがあります。
- 社会的な信頼度が高まる
- 節税対策がしやすくなる
- 有限責任になる
- 決算月が自由に決められる
この記事では、以下のような個人事業主が会社設立する際の基礎知識について解説します。
- 個人事業主が法人化するメリット・デメリット
- 個人事業主が法人化するのに適したタイミング
- 会社設立をする手続きの流れ
大阪で会社設立を検討されている方は、【代行手数料無料】かつ【最短即日設立可能】なハートランド税理士法人へぜひご相談ください。
創業融資の審査通過率100%継続中の資金調達のプロフェッショナル集団が、会社設立後の資金調達から販路拡大まで徹底的にサポートさせていただきます。
個人事業主の法人化(法人成り)とは

法人化とは、個人事業主が自身の事業を会社として継承することを指します。法人化は「法人成り」とも呼ばれており、これは個人事業主が法人に変わることを意味します。
2023年10月1日から導入されたインボイス制度は個人事業主に大きな影響を与えるため、法人化を検討する個人事業主が増えています。
法人化することで法人税の適用や役員報酬の設定などが可能になり、経営の柔軟性が増すメリットもあります。なお、法人化は事業拡大や資金調達を考える際に検討されることが多いです。
個人事業主が会社設立をする4つのメリット
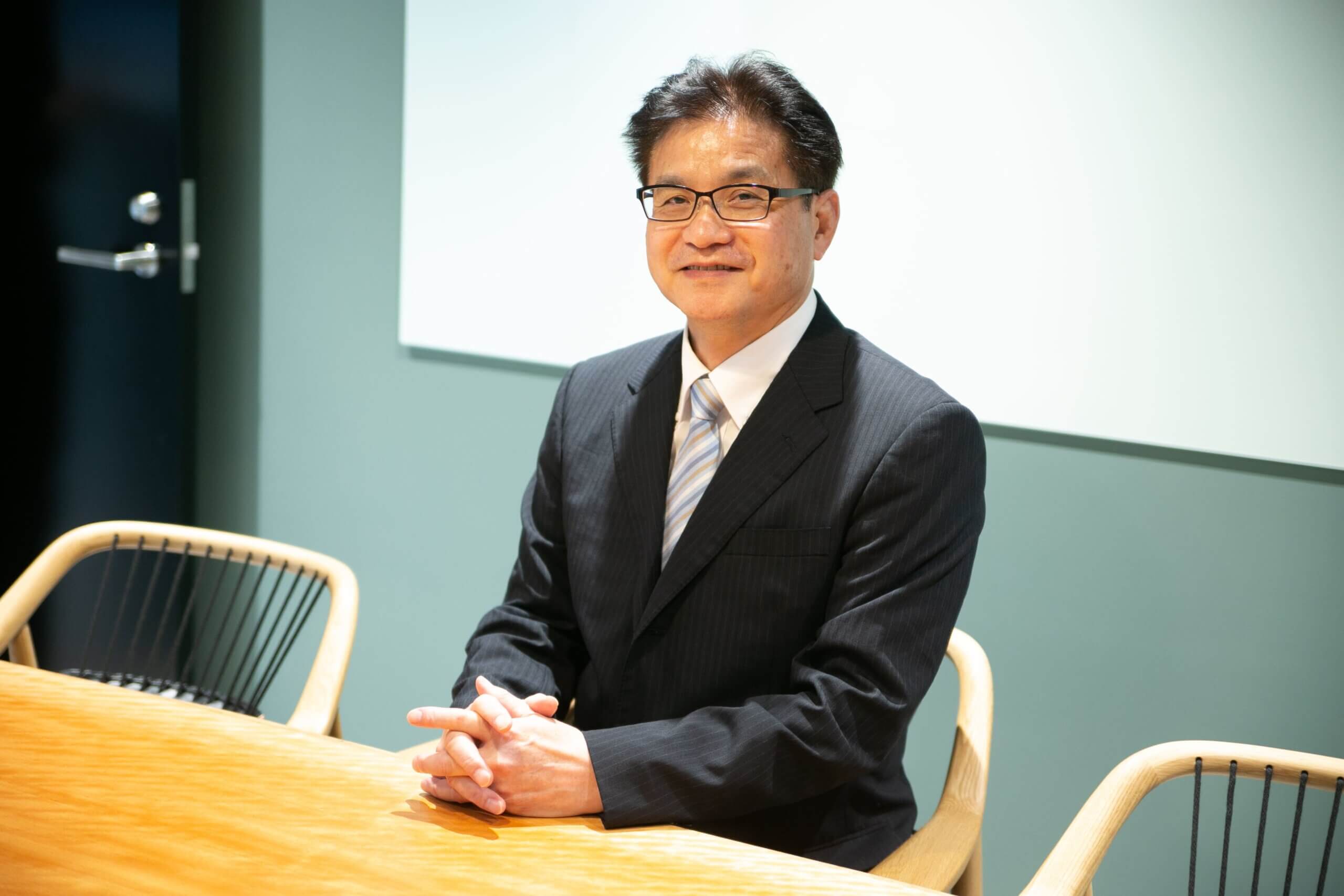
次に、個人事業主が会社設立をするメリットを4つ紹介します。
- 社会的な信頼度が高まる
- 節税対策がしやすくなる
- 有限責任になる
- 決算月が自由に決められる
それぞれのメリットについて詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
社会的な信頼度が高まる
会社を設立する際には、商号(社名)や所在地、資本金などの情報を法務局に提出して登記する必要があります。登記された情報は一般の人でも閲覧できるため、会社としての責任を負い、社会的な信用度を高めることに役立ちます。
例えば、個人事業主と契約を結ばない企業などにも、法人化することで取引ができるようになり、事業を拡大する上で大きな利点があります。
節税対策がしやすくなる
個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なります。個人事業主は所得税がかかり、法人は法人税が課されます。個人事業主の場合、所得税は累進課税となるため所得が増えると税率が段階的に上がり、最大の税率は所得税率最大45%に追加で住民税10%=55%になります。
対して法人税の場合、資本金が1億円以下かつ所得が800万円を超える法人の税率は23.2%、所得が800万円以下なら15%です。所得が増えるほど、法人設立による節税効果は高まります。
他にも、法人化すると節税に関して以下のようなメリットもあります。
- 役員報酬を損金計上できる
- 退職金を損金計上できる
- 赤字を10年繰り越せる
- 生命保険料を経費にできる
有限責任になる
個人事業主の場合、責任は全て個人にあります。経営が悪化した場合には、未払いの仕入先への支払い、借入金、滞納した税金なども個人の負債となります。一方、法人の場合は、個人保証による借り入れを除けば「有限責任」となります。
つまり、代表者個人がすべての責任を負う必要がなくなります。出資額以上の支払い義務は発生せず、個人の資産は保護されます。万が一の場合でも、リスクを最小限に抑えられる点に関しても、個人事業主が法人化することには大きな利点があります。
決算月が自由に決められる
個人事業主の場合、法律によって事業年度は1月~12月と決められているため、決算月は自動的に12月に設定されます。一方、法人の場合は事業年度の決算月を自由に設定できます。
法人の繁忙期と決算月が重ならないようにするなど、都合に合わせて調整することが可能です。
個人事業主が会社設立をする3つのデメリット

個人事業主が会社設立をするデメリットには、以下3つのようなものがあります。
- 会社設立の際に費用がかかる
- 社会保険に加入する必要がある
- 売上に関わらず税金がかかる
それぞれのデメリットについて詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
会社設立の際に費用がかかる
個人事業主の開業と異なり、会社設立にはさまざまな費用がかかります。法人の形態によって設立費用は異なり、株式会社の場合は「資本金額×0.7%」が法務局での法人登記手続きに必要な登録免許税としてかかります。ただし、算出される金額が15万円に満たない場合は15万円が必要です。
一方で、合同会社の場合は「資本金額×0.7%」で、算出された金額が6万円に満たない場合は6万円になります。
なお、法人設立は資本金1円から可能なものの、初期費用に運転資金3ヵ月分を加えた金額を準備しておくことが望ましいとされています。
社会保険に加入する必要がある
法人化すると、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入することが義務づけられます。さらに、法人は社会保険料の半分を負担しなければなりません。
そのため、法人化すると法定福利費(社会保険料の法人負担分)が増え、手続きなどの事務負担も増えてしまいます。もちろん、これらの保険に加入することで、従業員の健康や将来を守れるものの、少なくない支出になることはデメリットと言えるでしょう。
売上に関わらず税金がかかる
個人事業主が決算で赤字になった場合、所得税と住民税は免除されます。しかし、法人は赤字であっても法人住民税の均等割を支払わなければなりません。
均等割は資本金や従業員数によって決まる金額で、赤字であっても必ず支払わなければなりません。赤字であるにも関わらず税金を支払わなければならないというのは、法人のデメリットと言えるでしょう。
個人事業主が会社設立するのに適した3つのタイミング
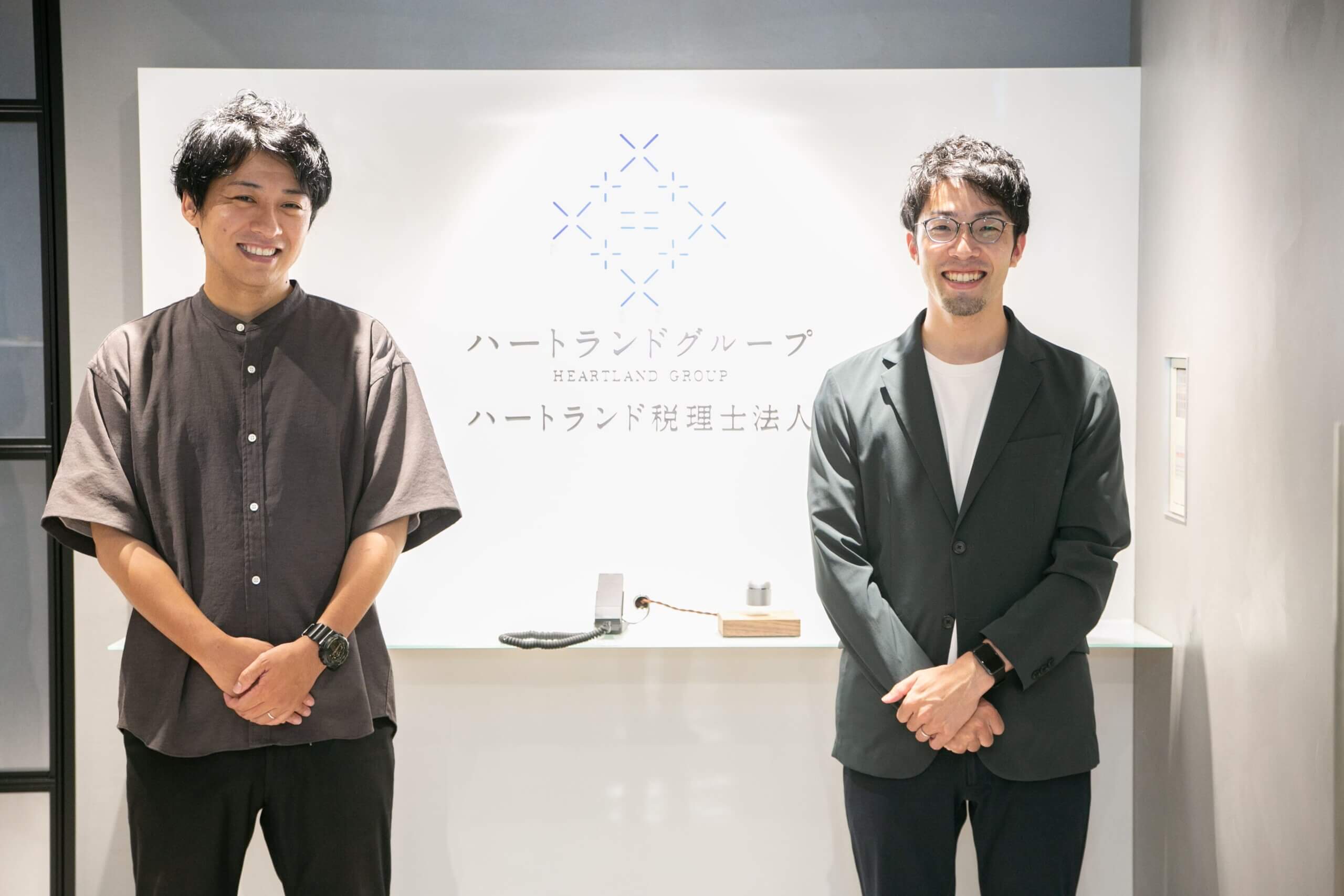
次に、個人事業主が会社設立するのに適したタイミングを3つ紹介します。
- 売上が1,000万円を超えるか事業開始から2年が経過したタイミング
- 所得が800万円を超えたタイミング
- 事業の拡大や雇用をしたいタイミング
それぞれのタイミングについて詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
売上が1,000万円を超えるか事業開始から2年が経過したタイミング
法人成りをすると、新設する法人は個人事業主とは異なる存在となります。したがって、個人事業主時代の売上高は関係ありません。その結果、新たに設立された法人には特例が適用され、消費税の納税義務が最大2年間免除されることになります。
つまり、法人成りをすると事業開始から2年間は消費税を納める必要がなくなる場合もあります。例えば、事業開始から2年後に法人成りをすれば、合計で最大4年間にわたって消費税の免除を受けられます。
所得が800万円を超えたタイミング
個人事業主の場合、累進課税のため所得が増えると税率も高くなります。一方で、法人税は所得に関係なく固定されています。具体的には、所得が800万円以下の場合は15%、800万円を超える場合は23.2%です。
ただし、役員報酬の設定額によっては毎月の社会保険料支払額が大きくなり資金繰りを圧迫する恐れもあるため注意が必要です。
事業の拡大や雇用をしたいタイミング
売上が少なくても、事業の拡大をしたいと思うタイミングであれば必要に応じて法人化するのがおすすめです。個人事業主のままでは、優秀な人材を雇用するための補助金が受けられないなど、事業の拡大にとっては法人化が必要な場合があります。
逆に、売上が高くなってきても一概に「法人化」しなくてはいけないわけではありません。自分の事業にとってメリットが大きいならば現状維持もあり得ます。法人化は、やりたいことを実現するための手段としても考えるべきです。
個人事業主が会社設立する手続きの流れ・手順

個人事業主が会社設立するための手続きは以下の流れで進みます。
- 会社概要を決める
- 【任意】会社の実印を作る
- 定款を作成し認証を受ける
- 資本金を払う
- 登記申請に必要な書類を準備する
- 会社設立の登記をする
それぞれの手続きについて詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
会社概要を決める
はじめに、会社概要を決めます。会社設立時には、以下の項目は決めておきましょう。
- 事業の目的や経営理念
- 商号
- 本店・本社の所在地
- 資本金の金額
- 発起人
- 発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 設立時に発行する株数
- 株式譲渡制限の有無
- 公告の方法
- 事業年度
- 設立時取締役・設立時代表取締役
また許認可を必要とする業種の場合、申請の際に具体的な記載が求められる場合もあります。
【任意】会社の実印を作る
会社設立時は、一般的に以下の印鑑を用意します。
- 代表者印(実印)
- 銀行印(最近の傾向では実印を銀行印とするケースも増えています)
- 角印
- ゴム印
商業登記では以前は実印の提出が必要でしたが、令和3年2月15日からはオンラインでの登録申請に限り、印鑑の提出は任意となりました。
定款を作成し認証を受ける
次に、会社の定款(ていかん)を作成し認証を受けましょう。会社概要を詳しく記した文書は、定款と呼ばれます。定款は、会社の基本ルールをまとめたものです。
株式会社の場合、定款の作成後に公証役場で定款が法律に則って作成されたことを証明してもらう必要があります。
資本金を払う
発起設立の場合は発起人、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役のうち誰か1人の銀行口座に出資金を払い込みます。この際、払い込んだ金額が「資本金」となります。
なお、資本金の銀行への払い込みは、定款の認証を受ける前であっても問題ありません。
登記申請に必要な書類を準備する
次に、会社の設立登記手続きを行います。登記手続きをするためには、まず登記申請書を作成し、必要な書類を添付して法務局へ提出する必要があります。登記申請書には、商業登記法で定められた項目が必要になるため、それに従って正しく作成されていなければなりません。
登記の専門家である司法書士に作成を依頼することが一般的です。登記手続きが終わると、会社の設立が正式に完了します。
会社設立の登記をする
会社の設立日は、基本的に法務局に登記申請書を提出した日となります。そして、登記手続きが完了すれば、登記完了証が発行されます。
登記完了証の交付と登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードの取得までには、登記申請後1週間から2週間ほどの時間がかかります。
大阪で会社設立ならハートランド税理士法人へ

本記事では、個人事業主が会社設立するメリットやデメリット、おすすめのタイミングを解説しました。
2023年10月1日から導入されたインボイス制度は個人事業主に大きな影響を与えるため、法人化を検討する個人事業主が増えています。
個人事業主が会社設立をすると、社会的な信用が高まったり節税対策になったりと多くのメリットがあります。しかし、法人化の手続きは複雑で手間や時間がかかってしまうことも少なくありません。
大阪で会社設立を検討されている方は、【代行手数料無料】かつ【最短即日設立可能】なハートランド税理士法人へぜひご相談ください。
創業融資の審査通過率100%継続中の資金調達のプロフェッショナル集団が、会社設立後の資金調達から販路拡大まで徹底的にサポートさせていただきます。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。













