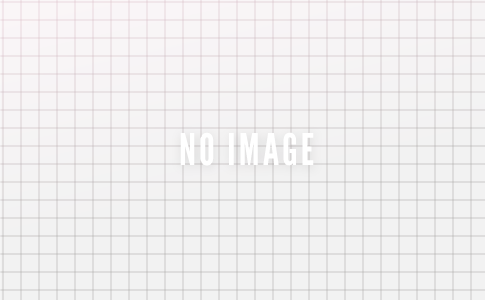<この記事は約 15 分で読めます>
相続の手続きで「税理士って本当に必要?」と悩んでいませんか?
財産がどれくらいあるのか分からない、申告の方法が複雑そう、時間が足りないと感じている方も多いでしょう。
本記事では、以下の4つについて解説します。
- 相続の税理士に依頼した方がいい6つのケース
- 税理士に依頼する必要がないケース
- 税理士に依頼する4つのメリット
- 相続の税務調査に強い税理士の探し方
また、税理士に依頼することで得られるメリットや、税務調査に強い税理士の選び方についても具体的に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
相続の税理士に依頼した方がいい6つのケース

相続に際して税理士への依頼が必要となるのは、税金の申告が関わる場合だけではありません。
財産の状況、心身の余裕、相続人同士の関係性など、さまざまな事情を総合的に考慮する必
要があります。
以下のようなケースでは、相続手続きを税理士に依頼することが強く推奨されます。財産の内容や状況によっては、専門的な判断や対応が必要になるため、早めの相談が安心につながります。
- 基礎控除を超えるか判断がつかない場合
- 準確定申告など税務手続きが発生する場合
- 財産内容が多岐にわたっていて複雑な場合
- 忙しくて時間的・精神的に余裕がない場合
- 相続人同士で遺産分割について争いがある場合
- 評価や取り扱いが難しい財産が含まれている場合
これらの項目に一つでも当てはまるなら、税理士の力を借りることで手続きがスムーズに進み、申告漏れや誤りによるリスクも軽減できます。
基礎控除を超えるかわからない場合
相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除がありますが、相続財産に不動産や非上場株式、名義預金などが含まれている場合、評価が難しく、自分で計算して判断するのは困難です。
基礎控除をわずかに超えるだけでも申告義務が発生し、過少申告や申告漏れはペナルティの対象になります。
税理士に相談することで、正確な評価と申告の要否を把握でき、安心して手続きを進められます。
判断に迷う方は、まず財産の一覧を持参して相談に行くことをおすすめします。
準確定申告が必要である場合
被相続人が死亡した年に所得があった場合、「準確定申告」と呼ばれる所得税の申告が必要になります。
これには医療費控除、年金、賃貸収入など多様な所得の把握と申告処理が必要となり、確定申告と同様に正確な計算と期限内の提出が求められます。
特に年の途中で亡くなった場合には、収入期間の区切り方や源泉徴収との整合性も考慮する必要があり、手間も大きくなります。
準確定申告が必要と判断された場合は、早めに税理士に委任して準備を始めるとスムーズです。
財産内容が複雑である場合
財産の中に複数の不動産や未上場株、貸付金、共有名義の財産などが含まれると、評価方法や名義整理に関して専門的な知識が必要です。
これらは民法上の遺産分割と税法上の評価で扱いが異なることも多く、相続人同士で認識がずれ、トラブルの原因になることもあります。
税理士が関与することで、法律と税制の両面から客観的な整理が可能となり、スムーズな手続きを促進します。
複雑な財産をお持ちの方は、初期段階で専門家の助言を受けることが重要です。
時間や心に余裕がない場合
相続手続きは書類収集から申告・納税まで多岐にわたり、通常でも数ヶ月を要します。
相続人自身が仕事や介護で多忙であったり、精神的な余裕がない中で正確な対応を求められると、ミスや申告漏れのリスクが高まります。
税理士に依頼すれば、必要な情報を伝えるだけで申告までを一貫してサポートしてもらえるため、精神的・時間的な負担を軽減できます。
「自分でできるか不安」と感じた時点で、早めの相談を検討しましょう。
相続分について争っている人がいる場合
遺産分割協議で相続人同士の意見が対立する場合、感情的な対立に発展することがあります。
このような状況下での相続税の申告や手続きは非常に難しくなります。
税理士が入ることで第三者的立場から法的・税務的観点で調整が可能となり、冷静な話し合いの土台を築く助けになります。
また、専門家の関与があることで他の相続人の理解や納得を得やすくなり、早期解決に繋がることもあります。
対立がある場合は、必ず専門家を交えて話し合いましょう。
評価が困難な財産がある場合
美術品、骨董品、同族会社株式など、評価が専門的な判断を要する財産は、相続税の計算において大きな課題となります。
市場価値が明確でない財産は、どのように評価して税務署へ申告するかで納税額に大きな差が生じます。
適正な評価を行わないと、税務調査で否認され、加算税を課されるリスクもあるため、慎重な対応が必要です。
こうした財産をお持ちの方は、評価実績がある税理士のサポートを得ることで、適切な処理が可能になります。
税理士に依頼する必要がないケース

以下のような場合は、相続税申告に税理士を依頼しなくても対応できる可能性があります。
- 財産内容がシンプルで、自力で評価や申告が可能な場合
- 相続税がかからないことが明確で、申告義務も発生しない場合
相続の内容や金額が一定の条件を満たす場合、専門家の関与なしでも正確に対応できることがあります。
それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
財産内容がシンプルである場合
相続財産が現金や普通預金、不動産1件など、種類や数量が限定的であれば、自力で相続税の申告を行うことも現実的です。
財産の評価が容易であり、計算ミスや申告漏れのリスクも比較的低いため、国税庁の「相続税申告書作成ソフト」などを活用することで、一般の方でも手続きが可能です。
ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを活用する場合は、その適用要件を誤解しやすいため、注意が必要です。
内容が明確で、相続人間のトラブルがない場合に限定されますが、費用を抑えたい方には選択肢の一つとなります。
相続税がかからないことが明確な場合
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であることが明らかであり、かつ非課税財産以外に特筆すべき資産が存在しない場合には、相続税の申告自体が不要となることがあります。
このようなケースでは、税理士に依頼する必要は基本的にありません。
ただし、申告が不要であっても、相続人間での遺産分割協議や名義変更の手続きは必要です。
財産の額や種類に確信が持てない場合は、念のため税理士や税務署に確認することで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
税理士に依頼する4つのメリット

相続税の申告や手続きにおいて、税理士に依頼することで以下のような利点があります。
- 複雑な申告作業をスムーズに代行してもらえる
- 相続内容に応じた具体的なアドバイスが得られる
- 財産評価の工夫により合法的な節税が期待できる
- 万が一の税務調査にも専門家が対応してくれる
相続は一生に一度あるかないかの大きな手続きです。
税理士に依頼することで、ミスやトラブルのリスクを大きく減らすことができます。
以下で、具体的なメリットを詳しく解説します。
申告がスムーズにできる
相続税申告は書類の準備や財産評価、税額の計算など多くの工程が必要であり、法律知識が求められる分野です。
税理士に依頼すれば、複雑な申告手続きをスムーズに進めることができます。
特に、相続財産が多岐にわたる場合や、分割協議に時間がかかる場合には、プロによる進行管理が非常に役立ちます。
書類不備による手戻りや申告期限の遅れを避けるためにも、専門家のサポートは安心材料となります。
個別具体的な相談ができる
相続の状況は家庭ごとに異なり、一律のマニュアルでは対応しきれない課題が出てくることもあります。
税理士に依頼することで、相続人の人数や財産の種類、過去の贈与歴などをふまえた上で、最適な申告方法や節税策の提案を受けられます。
また、将来の二次相続まで見据えた設計を相談することも可能です。
ネットや本では得られない、オーダーメイドの助言が得られる点は大きなメリットです。
財産の評価額を下げて節税してもらえる
税理士は、法令の範囲内で財産の評価額を適切に見直し、結果的に相続税を軽減できる可能性があります。
たとえば不動産であれば、立地や形状、利用状況などをふまえて評価額を下げられるケースもあります。
また、配偶者控除や小規模宅地等の特例、非課税枠の適用など、各種制度の活用にも精通しており、自己判断で見落としがちな節税手段を的確に適用できます。
これにより、本来よりも多くの税金を納めてしまうリスクを避けられます。
税務調査の対応をしてくれる
相続税の申告後、税務調査が行われるケースも少なくありません。
調査では申告の内容だけでなく、過去の資金移動や贈与の履歴なども詳細に確認されます。
こうした場面でも、税理士が代理人として対応してくれることで、調査がスムーズに進み、不要なトラブルを避けることができます。
事前の申告内容に不備がないようチェックを受けることで、調査対象になりにくくする効果も期待できます。
相続の税務調査に強い税理士の探し方

相続税の申告を税理士に依頼する際は、以下のポイントを意識して選ぶことで、税務調査に強い信頼できる専門家を見つけやすくなります。
- 事前の無料面談で相性や対応力を確認する
- 相続税申告の実績を具体的に確認する
- 報酬体系が明確で、見積もりが丁寧である
- 費用の計算方法や追加料金の有無をチェックする
税理士にも得意分野があります。
相続税に特化した税理士を選ぶことで、複雑な手続きや調査対応にも安心して任せることができます。
依頼前の面談
税理士を選ぶ際には、まず面談を受けることが重要です。
面談を通して、専門性や対応姿勢、相続税に関する知識の深さなどを確認できます。
多くの税理士事務所では初回無料相談を設けているため、その機会に質問をぶつけてみましょう。
たとえば「相続税申告で注意すべき点は何か」「過去に対応した調査事例はあるか」などを聞くことで、信頼性を判断できます。
話しやすさやレスポンスの早さなど、コミュニケーション面も重要なチェックポイントです。
実績の確認
税理士の中でも相続税に特化した経験が豊富かどうかは、非常に大切な判断材料です。
国税庁の調査データによれば、申告件数の少ない税理士に依頼した場合、申告漏れやミスが生じる傾向があります。
そのため、「過去5年間に何件の相続税申告を担当したか」や「調査対応の経験があるか」といった実績を確認することが、税務調査を避けるためには有効です。
具体的な数値や対応事例を教えてくれる税理士ほど、信頼性が高いといえます。
税理士報酬の確認
税理士への報酬体系は事務所によって大きく異なります。
相続税申告は比較的高額な案件となるため、依頼前に報酬額の内訳や料金体系を確認しておきましょう。
たとえば「申告報酬」「調査対応費」「不動産評価の追加料金」などが発生する場合があります。
見積もりが不透明な場合や、費用説明が曖昧な場合は注意が必要です。
複数の事務所から見積もりを取り、費用とサービス内容のバランスを比較検討することが安心につながります。
費用の計算方法の確認
税理士の費用は、相続財産の総額や項目数、不動産評価の難易度などにより変動します。
したがって、費用の計算根拠や追加料金の発生条件などを事前に確認しておくことが重要です。
たとえば、「財産額の○%」という歩合制か、「定額+加算方式」かといった違いがあります。
また、税務調査が発生した場合の追加対応費用がどうなるかも確認すべきです。
契約書に明記されているか、事前に口頭で説明されるかをチェックしておきましょう。
大阪・東京で相続税の計算・申告にお悩みの方はハートランド税理士法人へご相談ください

相続手続きは、誰にとっても人生でそう何度も経験することではありません。
そのため、最初は「自分でできるかもしれない」と思われる方も多いのですが、実際には思っている以上に専門知識を要する場面が数多くあります。
特に、不動産の評価や遺産の分割、過去の贈与履歴の扱いなど、正しい判断を求められるケースでは、税理士のサポートが不可欠となります。
専門家に依頼することで、税金の負担を最小限に抑えるだけでなく、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
また、申告書の作成から提出、税務署とのやりとりまで一貫して任せることができるため、ご家族の精神的な負担も軽減されます。
ハートランド税理士法人では、こうした複雑な相続の場面で、依頼者様一人ひとりの状況に合わせたきめ細かな支援を行っています。
相続について「何から始めればいいかわからない」という段階でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。