<この記事は約 18 分で読めます>
起業を考えている人にとって、会社設立にあたってどの程度お金がかかるのかは気になる点かと思います。
会社設立に必要な費用は大きく分けて以下の7つです。
(1)資本金
(2)定款に貼る収入印紙代
(3)公証人手数料
(4)定款の謄本手数料
(5)登録免許税
(6)登記簿謄本代・印鑑証明書代
(7)行政書士や司法書士への報酬費
この記事では、以下のような会社設立費用の基礎知識について解説します。
- 会社設立に必要な7の費用とそれぞれの金額
- 株式会社を選択した方が良い3つのケース
- 仕訳に必要な会社設立費用の勘定科目
- 会社設立費用の仕訳方法
- 会社の維持に必要な4つの費用とそれぞれの金額
- 会社設立にかかる費用を安く抑える方法
東京・大阪で会社設立を検討されている方は、【代行手数料無料】かつ【最短即日設立可能】なハートランド税理士法人へぜひご相談ください。
創業融資の審査通過率100%継続中の資金調達のプロフェッショナル集団が、会社設立後の資金調達から販路拡大まで徹底的にサポートさせていただきます。
会社設立にかかる費用
前提として、会社設立にかかる総額は株式会社か合同会社かによって異なります。以下の表は株式会社と合同会社の設立にかかる費用をそれぞれまとめたものです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
| 登録免許税 | 15万円 もしくは資本金×0.7%の高い方 | 6万円 もしくは資本金×0.7%の高い方 |
| 定款用の認証手数料 | 3万円~5万円 | – |
| 定款の謄本手数料 | 1ページにつき250円 | – |
| 定款用の収入印紙代 | 4万円 ※電子定款は無料 | 4万円 ※電子定款は無料 |
| 総額 | 25万円前後 | 10万円前後 |
株式会社を設立する際は、資本金にもよるものの25万円ほどは必要です。一方で、合同会社であれば10万円ほどで会社の設立が可能です。
ただし、合同会社の場合は株式を発行できないため、資金調達の手段が限られる点には注意しましょう。
会社設立に必要な7つの費用とそれぞれの金額

会社を設立する場合、株式会社か合同会社のどちらかを選択することができますが、ここでは株式会社に必要となる7つの費用について、簡単に説明します。
(1)資本金
開業した時点で企業が所有している運転資金のことを、資本金といいます。
定款に定めた資金のことですが、平成18年に施行された新会社法により、現在は1円以上あれば会社を設立することが可能であるため、経営者が自由に金額を設定することができます。
そのため、資本金自体にはあまり意味はなく、開業にそれほど大きな影響を与えることはありません。
とはいえ、実際には開業後の収益や費用を予想して算定した運転資金をベースとし、資本金額を決めるのが一般的です。開業してすぐに収益が上がらないことを想定し、売り上げがなくてもしばらくは運営ができるよう、数カ月単位の予算を確保しておくべきでしょう。
(2)定款に貼る収入印紙代
会社の憲法ともいわれる定款は、商号や事業内容、役員数など、企業が活動を行う上の根本的な規則を定めたものを指します。
定款の書式は特に決まっていませんが、必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、記載していないと有効にならない相対的記載事項、記載しなくても良い任意的記載事項に分けて記載する必要があります。
定款を認証する際は収入印紙が必要となるため、紙ベースで提出すると印紙代4万円の費用がかかります。
しかし現在では、電磁的記録による電子定款も認められるようになったため、PDFでの提出も可能になっています。電子定款は収入印紙代が不要なので、会社設立費用を削減するのに役立ちます。
(3)公証人手数料
定款の認証は、定款に記載した本店所在地の所轄の公証役場で行います。
公証人に認定を受ける手数料として、5万円の費用がかかります。
(4)定款の謄本手数料
株式会社を設立する場合、公証役場に定款を提出し、公証人に定款認証を受けなくてはなりません。
最初に公証人から認定を受けた定款は原子定款とも呼ばれ、1部は公証役場で、1部は会社で保管します。
会社設立の際に登記申請を行う場合、公証役場で取得した定款を添付する必要があります。会社用の原子定款は保管用になりますので、添付する定款は謄本を取得しなくてはなりません。
謄本とはコピーのことで、その手数料は1ページあたり250円必要になります。例えば、定款が5枚の場合は1250円の費用がかかることになります。
(5)登録免許税
会社設立の登記申請を行う際に、法務局に支払う費用が登録免許税です。
登録免許税法で定められている国税で、法務局で申請するときに納付分の収入印紙を購入する、または金融機関や税務署で現金納付を行います。
株式会社の場合は資本金額の0.7パーセントを支払いますが、この金額が15万円に満たない場合は15万円を支払わなくてはなりません。
登録免許税が15万円を超えるには資本金が2143万円以上かかりますが、初めて会社を設立する場合、ここまで資本金を投入することはほとんどありませんので、登録免許税は15万円と覚えておくと良いでしょう。
(6)登記簿謄本代・印鑑証明書代
銀行口座を開設する場合や、契約を締結する際に必要になります。
登記簿謄本は書面請求で600円、印鑑証明書は450円の費用が必要になります。
(7)行政書士や司法書士への報酬費
会社設立の手続きをスムーズに進めるため、行政書士や司法書士へ依頼することもできます。
会社の登記を行うのは司法書士が専門分野となるので、登記手続きを依頼したい場合は司法書士へ、定款作成や定款認証など許認可手続きを依頼したい場合は行政書士を選ぶと良いでしょう。
登記手続きの代行は司法書士しか行えませんが、税務処理や会計処理の相談などは対応できませんので、登記手続きだけを依頼するときに活用するのがおすすめです。税務や決算についての相談は税理士へするのが良いでしょう。
【関連】会社設立の登記申請までしてくれる?司法書士を利用するメリットや各士業の役割とは
株式会社を選択した方が良い3つのケース
会社設立に多少費用がかかっても株式会社を選択した方が良いケースには、主に以下の3つのケースが当てはまります。
- 信頼性を得たい場合
- 将来的に上場を視野に入れている場合
- さまざまな方法で資金調達をしたい場合
それぞれのケースを詳しく紹介します。
信頼性を得たい場合
会社の信頼性をより高めたい場合、合同会社よりも株式会社を選ぶと良いでしょう。以下2つの理由から、現在の日本では合同会社よりも株式会社の方が社会的な信頼性が高いと言われています。
- 合同会社は株式会社よりも閉鎖的な側面があるため
- 株式会社と比べ認知度が低いため
合同会社には決算公告の義務がなく、事業の展開も代表社員の意志によって行われます。外部から見ると内情を把握する手段が少なく、資金繰りや経営状況の判断が難しい側面があります。
また、日本では合同会社の認知度は株式会社に比べまだ高くありません。合同会社は2006年に認められるようになった比較的新しい形態の会社のため、まだ認知度や信頼性が低い傾向があります。
将来的に上場を視野に入れている場合
将来的に上場を視野に入れている場合は株式会社を選びましょう。合同会社では株式を発行する制度がなく、一切発行できないためです。そのため、合同会社では会社が成長しても上場は目指せません。
合同会社から株式会社への変更は可能なものの、組織変更の手続きや株式会社としての登記には手間やコストがかかります。
さまざまな方法で資金調達をしたい場合
さまざまな方法で資金調達をしたいと考えている場合も、株式会社を選択すると良いでしょう。合同会社では、以下2つの理由から資金調達が株式会社に比べて難しい側面があります。
- 合同会社は株式会社よりも信頼性が低いとされる場合がある
- 株式を発行できない
株式会社であれば出資や融資だけでなく補助金や助成制度などさまざまな選択肢から資金調達の方法を選べます。将来的に資金調達を受けたいと考えている場合は、株式会社を選んでおきましょう。
仕訳に必要な会社設立費用の勘定科目

会社設立費用について説明しましたが、会計処理を行う場合、どのような勘定科目で仕訳をすれば良いのでしょうか。
会社設立費用は大きく分類すると、以下の2つに分かれます。
- 創立費
- 開業費
設立前から登記するまでの費用が創立費で、登記後から運営を開始するまでの費用が開業費となります。
各費用には一体どのような項目が含まれるのでしょうか。
創立費
会社を設立登記するまで支出した費用を創立費といいます。
会社設立前に支出している費用にあたります。ちなみに上記で説明した費用は、すべて創立費に含まれますが、資本金は含まれませんので注意が必要です。
また、ほかにも創立費として計上できる費用があります。項目としては以下のとおりです。
- 定款に記載して創立総会の承認を受けた発起人報酬費用
- 株式募集のための広告費
- 株券や目論見書などの印刷費
- 事務所の賃借料
- 発起人の報酬
- 設立事務に使用する使用人の給料
- 金融機関や証券会社の取扱手数料
- 株主総会の開催費用
- そのほか会社設立事務に関する費用
開業費
会社設立手続きの完了後、営業を開始するまでに必要となった費用を開業費といいます。
営業を始めた後に発生した費用は対象外となります。
気を付けなくてはならないのが、開業するために発生した費用であっても、すべて開業費に計上できるわけではありません。開業のために必要な費用だとしても、特別に支出した費用でなければ経常的費用となるため、別の費用として計上するのがルールとなっています。
開業費として計上できる特別支出の項目は以下のとおりです。
- 開業に必要な備品の購入費
- 広告宣伝費
- 市場調査費
- 旅費交通費
- 通信費・水道光熱費
- 接待交際費
パソコンやプリンタなど10万円以上する高額な備品は、減価償却が行えるため、開業費ではなく固定資産として計上しましょう。
創立費や開業費は「繰延資産」になる
創立費や開業費の勘定科目は「繰延資産」として扱われます。繰延資産は任意の期間にわたって経費として計上できるため、新設された会社にとって有用な勘定科目です。
つまり、必ずしも設立時の事業年度に経費として計上する必要はありません。利益が出た事業年度まで経費を繰り越し、計上したい事業年度に経費として処理することが可能です。
会社設立費用の仕訳方法

会社設立費用の仕訳方法は以下のとおりです。
- 借方に現金(資産)を、貸方に資本金(資本)を計上します。
- 次に、設立前に必要となった費用を借方に創立費(資産)として、貸方に現金(資産)計上します。
- 開業費も同様に借方に開業費(資産)、貸方に現金(資産)で計上します。
- 決算時に繰延資産を償却する場合、借方に創立費、または開業費償却(費用)、貸方に創立費、または開業費(資産)として計上します。
開業費と創立費は、会計上償却期間が決まっていますが、税法上は任意償却となるので、納税者が自由に金額を決められます。
そのため、赤字の場合は償却計上を行わず、利益が出てから償却計上を行うことも可能です。
会社の維持に必要な4つの費用とそれぞれの金額
最後に、会社を設立した後、維持するために必要な費用を4つ紹介します。
- 税金
- 専門家への報酬
- 社会保険料
- その他の維持費
それぞれにかかる金額も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
(1)税金
法人になると、経営が赤字であっても一定額の税金を納めなければいけません。個人事業主の場合は、利益の額によっては無税になることもありますが、会社ではまったく税金を支払わない年はありません。つまり、会社にとっての税金は固定費となります。
会社の規模が小さくても、最低でも法人住民税(均等割)として約7万円を納税する必要があります。また、以下のような場合は支払う必要のある金額は大きくなるので注意が必要です。
- 会社が従業員を50人以上雇用した
- 別のエリアに支店や営業所を構えた
- 資本金が1千万円を超えた
会社を設立する際は事業だけでなく節税対策も考慮し、最適な従業員数や資本金額を検討しましょう。
(2)専門家への報酬
会社の維持費として、専門家への報酬も考慮すべきです。
会社は、事業年度の終わりには必ず決算書を作成して税務署などに提出する必要があります。しかし、決算書の作成には会計や税務に関する専門知識が必要であり、素人が一人で取り組むことは難しいです。そのため、税務の専門家である税理士に決算作業を任せることが一般的です。
顧問税理士の月々の報酬額は人によって異なりますが、一般的には月額3~5万円ほどかかります。
なお、顧問税理士への報酬額は会社の売上規模などによって大きく異なることがあります。
(3)社会保険料
法人は社会保険に加入することが義務づけられているため、社会保険料も維持費として計上すべきです。社会保険料は、法人を設立した時点から売上や利益に関係なく発生する固定費です。
会社が負担する社会保険料の額は、役員や従業員の数、役員報酬や給与額によって異なります。社員1人に対して会社が負担する社会保険料の目安は、社員の給料の約15%ほどです。例えば、30万円の給料を支払っている社員を雇っている場合、会社は約4万5千円の社会保険料を負担することになります。
また、個人事業主でも5人以上の社員を雇う場合は一定の業種を除いて社会保険料を支払う義務が生じます。
(4)その他の維持費
その他の維持費として、以下のような費用がかかります。
- 事務所の賃借料
- 事務所の光熱費
- 在庫管理費
- 社員への給与
- 社員の福利厚生費
- その他の士業に対する顧問報酬
会社は、設立だけでなく維持にもさまざまな費用がかかることを考慮しておきましょう。
会社設立にかかる費用を安く抑えるには補助金や助成金を活用するのがおすすめ
会社設立にかかる費用を安く抑えたいなら、主に以下の団体が提供している補助金や助成金を活用するのがおすすめです。
- 経済産業省
- 厚生労働省
- 地方自治体
- 民間団体
補助金や助成金は返済の義務がないため、会社設立時には大きく役立ちます。自分のニーズに合った補助金や助成金を探してみてください。
大阪で会社設立するなら【代行手数料無料】かつ【最短即日設立可能】なハートランド税理士法人へお任せください
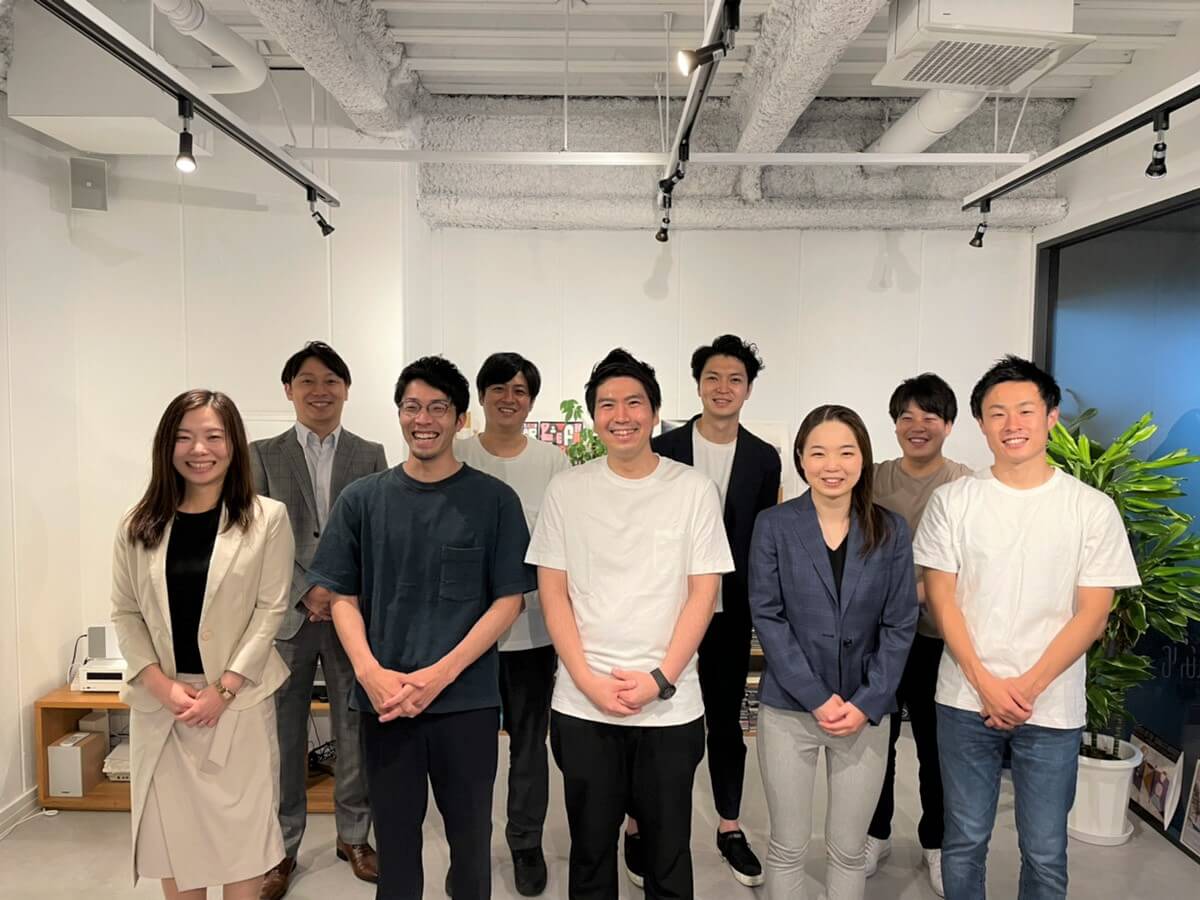
会社設立費用として計上できる創業費や開業費は、通常行う仕訳処理とは大きく異なる勘定科目です。
創立費は原則として、支出時に費用として処理することができますが、繰延資産として計上することが可能なため、会社が利益を出したときに償却処理をすることを覚えておくと良いでしょう。
東京・大阪で会社設立を検討されている方は、代行手数料無料かつ最短即日設立可能なわたしたちハートランド税理士法人へぜひご相談ください。
創業融資の審査通過率100%継続中の資金調達のプロフェッショナル集団が、会社設立後の資金調達から販路拡大まで徹底的にサポートさせていただきます。
【関連】大阪で会社設立するなら【手数料無料】かつ【最短即日設立可能】なハートランド税理士法人へお任せください
【関連】審査通過率100%継続中!大阪で創業融資の申請代行・サポートならハートランド税理士法人へご相談ください

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。












