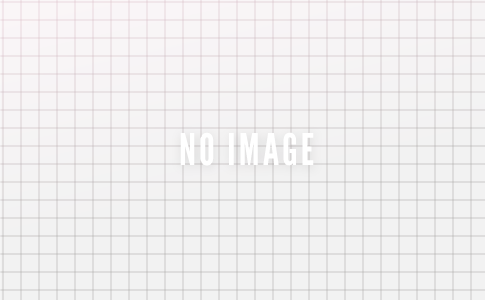<この記事は約 14 分で読めます>
相続した財産は、すべて課税対象になるというわけではありません。
中には「非課税財産」に該当し、相続税の課税対象にならないものもあります。
しかし、どういったものが非課税財産なのか、分からない方も多いはずです。
そこでこの記事では、
- よくある5つの非課税財産
- 特殊な2つの非課税財産
- 被相続人が相続人の生前にできる非課税対策
について、詳しく解説します。
相続額が3,600万円以下なら相続税はかからない
 非課税財産についてお話する前に、まずは相続税の基本的なルールをおさらいしましょう。
非課税財産についてお話する前に、まずは相続税の基本的なルールをおさらいしましょう。
相続税には基礎控除額があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
この金額以下の財産を相続した場合には、相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は4,800万円となり、相続財産が4,800万円以下であれば相続税はかからないということになります。
さらに、相続財産の総額が3,600万円以下であれば申告の必要もありません。
日本ではこのルールによりほとんどの世帯に相続税が課税されていませんが、もし基礎控除額以上の財産を相続する場合には、特例や控除をうまく使うことが大切です。
よくある5つの非課税財産

非課税の財産として、多くの人にとって該当することが多いのは、以下の5つです。
- 日常的に礼拝している財産
- 特定の法人や組織に寄付した財産
- 生命保険金の一部
- 退職手当金の一部
- 精神又は身体に障害のある者に対して支給される給付金を受け取る権利
生命保険金や退職手当金のように、非課税財産の中でも「対象になる部分」と「対象にならない部分」があるため、違いを知っておく必要があります。
順番に見ていきましょう。
日常的に礼拝している財産
日常的に礼拝している財産は、非課税財産に該当します。
具体的には、以下のものです。
- 墓地・墓石
- 仏壇・仏具
- 神棚
- 庭内神し(不動尊といったご神体をまつっているもの)
ただ、礼拝に関する財産でも金でできた仏像のように、それ自体に金銭的価値のあるものは相続税の対象です。
非課税かどうかは「売ってお金に変えられるかどうか」が判断基準です。
個人所有の仏具や墓石などは、お金を出して買いたいと思うことはありません。
そのため非課税となり、相続税の課税対象とはなりません。
特定の法人や組織に寄付した財産
寄付した遺産は特例が適用され、相続税が非課税となります。
ただ、寄付先はどこでもいいわけではなく、国や地方公共団体・公益法人(例:ユニセフ・日本赤十字など)といった、寄付先として認められている場所でないといけません。
相続税の特例は、他にもあります。詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
寄付による特例は、相続税の申告期限までに寄付することが適用条件です。
さらに公益信託の信託財産も、相続税の申告期限までに信託財産にするために支出すれば非課税となります。
生命保険金の一部
生命保険金の一部も、以下の計算で求められる金額まで非課税です。
<非課税の生命保険金の計算式>
・500万円✖️法定相続人の人数
ただ、保険金の中でも、相続人以外の人が取得した死亡保険金及び満期保険金は例外です。
被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、受取人が誰かは関係なく所得・相続・贈与税のいずれかが課税されますが、相続税には上記の非課税枠があります。
退職手当金の一部
被相続人の死亡によって支払われる退職手当金は、本来「みなし財産」扱いであり、課税対象です。
しかし、退職手当金には非課税枠が設けられています。非課税限度額の計算式は以下の通りです。
<退職手当金の非課税限度額の計算式>
・非課税限度額=500万円×法定相続人の人数
すべての相続人が受け取った退職手当金の合計額が非課税限度額以下なら、相続税の課税対象にはなりません。
ただ、相続人以外の人が取得した退職手当金は非課税にならないため注意しましょう。
精神又は身体に障害のある者に対して支給される給付金を受け取る権利
「心身障害者扶養共済制度」に基づき、支給される給付金のことです。
心身障害者の保護者が死亡した場合に、給付金が支給されます。
給付金の受け取り条件は、「心身障害者の保護者(被相続人)が障害者の生前に共済に加入していること」です。
受給権(給付を受け取る権利)は相続税・所得税の対象ですが、心身障害者扶養共済制度の対象の給付金は非課税となります。
特殊な2つの非課税財産

ここまでに解説したものだけでなく、以下のものも非課税財産です。
- 公益を目的とする事業に使われることが確実な財産
- 個人経営の幼稚園事業に使用されており、一定条件を満たす財産
ほとんどの方にはあまり関わりのない非課税財産ではありますが、頭の片隅に置いておきましょう。
公益を目的とする事業に使われることが確実な財産
公益を目的とする事業に使われる財産とは、以下のものをいいます。
- 宗教(お寺や神社、仏閣)
- 慈善事業
- 学術(学校経営)
非課税になるのは、事業に使われるもののみです。
財産の中で収益の発生する部分は、該当しない可能性が高いので注意しましょう。
個人経営の幼稚園事業に使用されており、一定条件を満たす財産
幼稚園経営者の死亡により運営事業を継承し引き継いだ財産のうち、教育用の財産は非課税となります。
対象となる運営事業は、幼稚園等(学校教育法に規定される私立の保育園・幼保連携型認定こども園)に限定されます。
非課税になるには、以下の条件も満たす必要があります。
| 非課税になる条件 | 詳細 |
| 確実に事業継続できると認められるもの | 運営事業の相続人が経営を継続できる |
| 教育用財産として届け出ている | 必要事項を記入した「教育用財産の届出」を、使用開始した4ヵ月以内に所轄税務署長へ提出している |
| 罰金を課せられていない | 所得税・相続税・贈与税についての重加算税がない (相続開始年〜5年前までの期間) |
| 家事充当金と給与が適正額 | 家事充当金(事業主本人の給与相当額)が、所轄税務署長の認定の受けた適正額以内 (相続開始年〜5年前までの期間) |
| 区分経理が行われている | 事業所得に関係する総収入額と必要経費を区分経理し、青色申告申告制度に基づいて保存 |
| 青色申告書を連続して提出している | 相続開始の5年前から青色申告書を提出 |
| 施設を目的外で使っていない | 相続開始の5年前から他の目的では使っていない (親族の家事・私的な担保としての利用もなし) |
| 目的外の支出がない | 相続開始の5年前から運営事業以外の目的で支出していない |
相続・遺贈で取得していることが非課税の条件なので、幼稚園事業を生前贈与で引き継いでいる場合は非課税にはなりません。
被相続人が相続人の生前にできる非課税対策
相続税の非課税対策は、被相続人が生きているうちに行うことでより高い効果を発揮します。
こちらでは、被相続人が相続人の生前にできる非課税対策を4つ紹介します。
年間110万円以下の贈与
被相続人が子や孫に自分の財産を譲る場合には贈与税がかかります。
ただし、贈与税には、年間110万円までの贈与は非課税となる暦年贈与という制度があります。
この制度を利用し、被相続人が生きているうちに毎年110万円以下の贈与を継続することで、相続財産を計画的に減らし、相続税の負担を軽減できます。
また、贈与は子や孫だけではなく特定の誰かに行うことも可能です。
暦年贈与の際には、贈与契約書を作成するなどして贈与の証拠を残すこと、贈与を受けた人が自由に使えるようにすることも大切です。
ちなみに令和6年以降に贈与される財産は、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算対象となるため、注意してください。
親または祖父母から、子・孫への贈与
60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子もしくは孫に贈与を行う際には、「相続時精算課税制度」を使うことができます。
贈与税と相続税を一体化する考え方で、この制度を選択すると、一定額までの贈与は贈与税を支払わずに済み、代わりに相続時にまとめて相続税として精算することが可能です。
累計2,500万円までの贈与に対して非課税枠が設けられていますが、贈与額が2,500万円を超えた場合、超えた部分には一律20%の贈与税が課税されます。
また、贈与者が亡くなった際には、贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、既に支払った贈与税額を控除して相続税を納付します。
特に将来値上がりが予想される不動産や株式などの財産に関しては、早期に贈与することで、値上がり後の相続税負担を回避できるでしょう。
ただし、生前贈与の際に暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを選ぶか迷われる方も多いと思いますが、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税に戻すことはできない点に注意が必要です。
教育資金および結婚・育児のための資金の一括贈与
親や祖父母から子や孫に対して、教育資金や結婚・育児資金をまとめて贈与する場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度はもうひとつあります。
この制度は、子や孫のライフステージにおける経済的な支援を目的としており、贈与者にとっては相続税対策にもつながる可能性があります。
「教育」を目的とした場合と「結婚・育児」を目的としたものがあるので、ひとつずつ解説します。
教育資金の一括贈与
親や祖父母から30歳未満の子や孫への教育資金の一括贈与は、1,500万円まで非課税となります。
ただし、「30歳まで」という制限があるため、贈与を受けた人は、30歳までに教育資金として使用しなければなりません。
学校等における入学金、授業料、教材費などの教育費だけではなく、学習塾、習い事、スポーツなどに使う場合も教育資金としてみなされます。
この制度を利用する場合は、教育資金として使用した証明書類の提出が必要である点や、30歳までに使い切れなかった残額は贈与税の課税対象となる点に注意してください。
結婚・育児資金の一括贈与
子や孫に対して結婚・育児を目的とした贈与も1,000万円まで非課税ですが、結婚資金に関しては300万円が上限です。
贈与を受けた人は、50歳までに結婚・育児資金として使用しなければならないうえ、受贈者の前年所得が1,000万円以下の場合のみ適用となります。
主に結婚式や新生活費用をはじめ、出産費用、育児用品購入費、保育料などが対象です。
教育・結婚・育児資金の一括贈与は、いずれも贈与税の申告が必要であるうえ、専用の金融機関口座を開設し、資金を管理する必要があります。
配偶者へ居住用の不動産を贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合、2,000万円まで非課税となります。
この特例は「配偶者控除」と言われており、利用することで、夫婦間の居住用不動産の移転をスムーズに行うことができます。
相続税の配偶者控除と併用できる点は魅力ですが、同一の配偶者からの贈与は一度きりであるため注意してください。
このように、被相続人が生きているうちに生前贈与を行い、特例や控除をうまく活用することで最終的に支払う相続税を軽減できます。
条件に当てはまる場合は、申請方法や注意点も知って節税にお役立てください。
東京と大阪で相続税の相談ならハートランド税理士法人へ

相続税は非課税になるものも多く、税負担を減らすことが可能です。
ただ、非課税になる条件は複雑ですし、申告手続きも必要で分からないことも多いでしょう。
相続税の申告や非課税については、自分で調べるより専門家に相談するのが確実です。
このサイトを運営する弊社「ハートランド税理士法人」では、相続・贈与に関する相談も受け付けています。
東京と大阪にお住まいで相続税について分からないことがある場合は、お気軽にご相談ください。
【関連】相続税に関する控除の種類一覧まとめ!各制度を税理士が解説
【関連】相続税と贈与税の違いは?どちらが損する?税理士が解説

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。